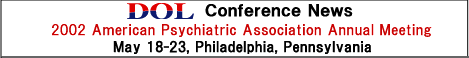|
子どもの精神疾患への沈黙を破って:国のイニシアティブ、早期発見、
および新たな薬物療法について(Part1) | | Breaking
the Silence of Children's Mental Illness: National Initiatives,
Early Detection, and New Pharmacotherapies, Part 1 |
|
|
子どもの精神疾患:従来の枠を踏み出して診断すること
| |
Mental Illness in Children: Diagnosing Outside the Box
| |
|
| 児童や思春期患者の診断には、大人と異なる以下の2つの特性を考慮する必要がある。①行動や症状が状況依存性である。②急速に変化する発達段階にあるため病像の
多様性が生じる(ADHDから気分調節の困難さを経て双極性障害BPDへの移行)。BPD患 者の子の研究で認められる深い病理、ADHDとBPD等の多様な重複診断を報告した。
| |
|
児童精神医学における非定型抗精神病薬:十分に計画された試験での有用性について
| |
Atypical Antipsychotics in Pediatric Psychiatry: Efficacy
in Well-Designed Trials | |
|
| 様々な児童・思春期精神障害に対して、非定型抗精神病薬を用いての二重盲検比較試験が行われてきた。小児分裂病へのclozapine、行為障害や自閉症へのリスペリドン、トウレット障害へのziprasidoneの有用性が示す報告が紹介された。多くのオープン試験でも、非定型抗精神病薬の有効性と忍容性が総じて示されており、対照との比較試験での追認が不可欠である。
| |
| |