|
Fischbach博士は自分が2002年に3つの主要な学会、すなわち米国精神医学会、米国神経学会、米国神経外科学会において講演をする予定であることから話を始めた。このように彼の講演の聴衆が多様であるということは、様々な臨床的な進歩の基盤にある基礎科学の多くが共通しているという事実を、異なる医学領域の専門家たちが理解してきていることを反映している。
彼は、ジグムント・フロイトの研究が電気生理学から心理学的体系化へと移行していったのはフロイトが自分の研究結果を精神生活理論のなかに位置づける必要があったからであると述べた。これに対して、今日の研究者たちが認知についての理解や精神生活に関する学説を塗り替えていくためには、新しい精神病理学や精神薬理学についての知見を用いていくことになると思われる。
Fischbach博士は話の残りの時間を用いて、既知の神経変性の多様性(表参照)に関する議論のなかで、基盤となる共通の見解を提示している。これらの神経変性はいずれも多少ともアポトーシスによる神経細胞の脱落をどのように促進、あるいは抑制するかという問題と関連してくる。
|
様々なライフステージにおける神経変性
・ | 脳の加齢に伴う障害:アルツハイマー病、パーキンソン病
| ・ | より若年の成人における障害:ハンチントン病筋萎縮性側索硬化症、プリオン病 | |
・ | 小児の障害:脊髄小脳変性症テイサックス病、他の蓄積病 |
|
|
博士はこれらの一見多様な疾患の多くに適用し得る一般的な枠組を示した。
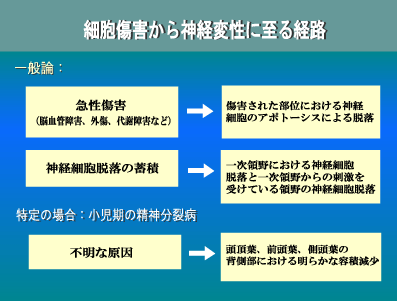
Fischbach博士によると、精神分裂病における容積減少はかなりの量に及び、1年に2〜3%程度の減少を来すことがある。これは特に頭頂葉背側皮質で顕著である。この知見から、彼は研究者たちが精神分裂病における思考障害を生じる脳部位(頭頂葉背側部)の手がかりを見出せるのではないかと期待している。脳部位が定まれば、その標的部位の神経細胞脱落を抑制したり、回復したりする研究も始まるであろう。
手がかりとなる部位を知ることが神経変性の抑制や回復の研究へとつながる事例はすでにパーキンソン病で認められる。パーキンソン病においては視床下核内の標的部位に与えた脳深部刺激が有効であるとのパイロットスタディが知られている。
例えば、電極刺入に際して機能的MRIを用いると、電極をきわめて正確に置くことができ、患者の対側の運動に関する症状を完全になくすことができる。研究の初期段階の結果によれば、長期にわたる電気刺激が神経賦活作用をもつことも示唆されている。
最後に、Fischbach博士は現在、種々の精神疾患で行われている多くの機能画像研究により、神経細胞の障害や脱落の生じている中心的な部位が明らかになるという考えを述べた。ひとたび、標的部位を特定できれば、その後の研究により神経細胞脱落の生じるメカニズムや、その脱落を抑制、回復し得る方法を明らかにすることができよう。
博士はパーキンソン病の研究を通じて得られた観察を述べて次のように話を結んだ:最初の臨床症状が認められた時点で、標的部位のおおよそ75%の神経細胞はすでに失われている。したがって、その疾患に罹患するリスクのある人や、疾患の初期段階にある人に対して、早期診断を行うことはケアの改善と予後の向上に決定的に重要である。
レポーター:
Elizabeth Coolidge-Stolz, MD
日本語翻訳・監修:昭和大学医学部精神医学教室助教授 三村 將
|
|