|
|
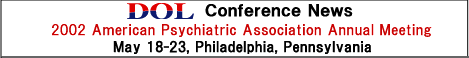 �@�@�@�@
|
|
|
| �@
| |
| �@ |
|
| Medical
Director
Bruce B. Dan, M.D. | |
| ���{��ő��ďC
�㓇����
�i���a��w��w��
���_��w���������j |
|
| |
�R���_�a��Ö@�ƐS���Ǐ�Q�F�d�v�Șb�� | | Antipsychotic
Therapy and Cardiovascular Disease: The Unfolding Story |
|
|
���_�����a���҂̐g�̓I�Ǝ㐫 |
|
Medical Vulnerability in Patients with Shcizophrenia
| | �@
|
| ���_�����a���҂͐g�̍����ǂ̗��������A���ϗ]�����Z���B�댯���q�Ƃ��Ă͔얞�A�������A�i���A�s�����Ȃǂ��l�����邪�A�R���_�a��̕���ł���ɑ�������B���_�����a�ɑ����Â̎��������Ɉێ����邩����ł���B
�@ | �@�@ |
|
Torsade de pointes, QT�ƍR���_�a��
| |
Torsade de Pointes, QT, and Antipsychotic Drugs |
| �@
|
| ����̍R���_�a��ɂ��QT���������ڂ���Ă���BQT�����͂�orsade
de pointes��ˑR���̂��������ƂȂ邱�Ƃ�����B�t�F�m�`�A�W���n�A���Ƀ`�I���_�W����QT�������N�����₷���BZiprasidone���������^�R���_�a���QT�������N�����ɂ����B
�@ | �@�@ |
|
���N�ւ̒��ӁF�R���_�a��Ö@�ɂ���ӕω�
| |
A Focus on Health: Metabolic Consequences of Antipsychotic
Therapy | |
�@
|
| ���^�R���_�a��ɂ����āAclozapine�ƃI�����U�s���ɂ��̏d�����Ɠ��A�a�̔��ǂ����ƂȂ��Ă��邪�A���X�y���h����ziprasidone�ł͏��Ȃ��B�����̗\�h�ɂ͒���I�ȑ̏d�v���ƐH�����܂߂������w�����d�v�ł���B |
�@�@ |
|
�R���_�a��Ɠ��A�a�F�u�w��������݂�����
| |
Antipsychotics and Diabetes: A Current Perspective on Epidemiology
| |
�@
|
| ���^�R���_�a��Ɠ��A�a�̔��������4,000�l�̐��_�����a���҂�ΏۂƂ��Ē��������B���̌��ʁAclozapine�A�I�����U�s���A�N�G�`�A�s���ł͒�^��Ɣ�r���ėL�ӂɓ��A�a�̔��������������Ƃ��킩�����B
�@ | �@�@ |
|
�R���_�a��ɂ���ėU������铜��ӕs�S�ƃC���X������R���̋@��
| |
Mechanisms of Antipsychotic-Induced Glucose Dysregulation
and Insulin Resistance | |
�@
|
| �ϓ��\�ُ�ɔ����������͗l�X�ȍ����ǂ̗U���ƂȂ�B���^�R���_�a��̃I�����U�s����clozapine�͒�^���X�y���h���Ɣ�r���ăC���X������R�����グ��������U������B�̏d�⌌���l�̑���ȂǏ\���ȊǗ����K�v�ł���B
�@ | �@�@ |
| |
|
| |
�A�h�q�A�����X�i���Ìp�����j�F�R���_�a�Âɂ�����]������̖��Ƃ��̉����@�̓���
| | The Adherence Challenge:
Chronic Issues and Emerging Solutions With Antipsychotic Therapy
| |
|
�A�h�q�A�����X�ɂނ��� |
|
Approaching the Adherence Challenge |
| �@
|
| ���_�����ł��g�̎����ł�����s����̊�����30���ɂ��̂ڂ�B���_�����a�ŕ���s����������炷�d�v�Ȉ��q�͖�܂̕���p�ł���B�A�h�q�A�����X�����P����ɂ͖w�I����ƐS���Љ�I������K�v�ł���B
�@ | �@�@ |
|
���_�����a�̖�ܑI���F����̈Ӗ� |
|
Pharmacologic Options for Schizophrenia: Implications for
Compliance | |
�@
|
| ���_�����a�ł͊�����5�N�ȓ��ɍĔ����闦��80���ɂ̂ڂ�B�f�|�܂͍Ĕ��댯�������������邱�Ƃ��m���Ă���B���������Ē�����p���ˌ^���^�R���_�a��͊��҂ł����܂ł���B
�@ | �@�@ |
|
������p���^�R���_�a��Ö@�̌��� |
|
Research Experience with Long-Acting Atypical Antipsychotic
Medication | |
�@
|
| ���^�R���_�a��͒�^�R���_�a��ɔ�ׂČ��ʂ��D�ꕛ��p�����Ȃ��B���X�y���h���̃f�|�܂��J�����ꂽ���A���^�R���_�a��ƃf�|�܂̗��҂̒����������Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B
�@ | �@�@ |
|
�Ō�T�C�h����F���_�Ɖ����@ |
|
Views from the Nursing Perspective: Problems and Solutions
| |
�@
|
| ���҂̎��Ò��f�ɂ͊Ō�t�Ƃ��ċ����S�������Ă���B�f�|�܂ɂ͊��҂Ǝ��ÎҊԂɎ��Ó������ł���Ȃǎ��Ìp���̂��߂̗��_�������A�Ĕ��h�~�̂��߂Ɋ��҂�����܂ł���B
| �@�@ |
| |
|
| |
�q�ǂ��̐��_�����ւ̒��ق�j���āF���̃C�j�V�A�e�B�u�A���������A
����ѐV���ȖÖ@�ɂ��āiPart1�j | | Breaking
the Silence of Children's Mental Illness: National Initiatives,
Early Detection, and New Pharmacotherapies, Part 1 |
|
|
�q�ǂ��̐��_�����F�]���̘g�ݏo���Đf�f���邱��
| |
Mental Illness in Children: Diagnosing Outside the Box
| | �@
|
| ������v�t�����҂̐f�f�ɂ́A��l�ƈقȂ�ȉ���2�̓������l������K�v������B�@�s����Ǐˑ����ł���B�A�}���ɕω����锭�B�i�K�ɂ��邽�ߕa���̑��l����������iADHD����C�����߂̍�����o�đo�ɐ���QBPD�ւ̈ڍs�j�BBPD���҂̎q�̌����ŔF�߂���[���a���AADHD��BPD���̑��l�ȏd���f�f������B
| �@�@ |
|
�������_��w�ɂ�������^�R���_�a��F�\���Ɍv�悳�ꂽ�����ł̗L�p���ɂ���
| |
Atypical Antipsychotics in Pediatric Psychiatry: Efficacy
in Well-Designed Trials | |
�@
|
| �l�X�Ȏ����E�v�t�����_��Q�ɑ��āA���^�R���_�a���p���Ă̓�d�ӌ���r�������s���Ă����B���������a�ւ�clozapine�A�s��Q�⎩�ǂւ̃��X�y���h���A�g�E���b�g��Q�ւ�ziprasidone�̗L�p�����������Љ�ꂽ�B�����̃I�[�v�������ł��A���^�R���_�a��̗L�����ƔE�e���������Ď�����Ă���A�ΏƂƂ̔�r�����ł̒ǔF���s���ł���B
| �@�@ |
| |
|
| |
�q�ǂ��̐��_�����ւ̒��ق�j���āF���̃C�j�V�A�e�B�u�A���������A
����ѐV���ȖÖ@�ɂ��āiPart2�j | | Breaking
the Silence of Children's Mental Illness: National Initiatives,
Early Detection, and NewPharmacotherapies, Part 2 |
|
|
�o�ɐ���Q�⑼�̏�Ԃ���̃G�r�f���X�Ɋ�Â��A��N�̐��_��Q�ɑ��鎡�Â̔��W
| |
Evolving Treatments for Psychiatric Disorders in Young Patients
with�@Evidence from Bipolar and Other Conditions |
| �@
|
| ���������ǂ̑o�ɐ���Q�͏]���M�����Ă����悤�ȋH�ȕa�Ԃł͂Ȃ��B�N�a���͑�l�����^�ŁA�ő����A�����o�߁A�����č�����Ԃɓ����t�����邪�A���̍���Ȑf�f�̑Ó������o�߁A���Ì��ʂ̌������玦�����B������܂ɉ����āA���^�R���_�a��̓��^�����Ï�̑I���ƂȂ낤�B
| �@�@ |
|
����������юv�t�����҂̍R���_�a��ɂ��Ö@�F�����������^�ł̈��S���������G�r�f���X�Ȃ̂��H
| |
Antipsychotic Pharmacotherapy in Children and Adolescents:
What Is the Evidence for Long-Term Safety? |
| �@
|
| �R���_�a��͖������_��Q�ɓ��^����邱�Ƃ������A�]���^�̒�^�R���_�a���������p�̏��Ȃ����̂��]�܂��B�����E�v�t�����҂ւ̍R���_�a�^���AEPS�̏��Ȃ����^�R���_�a��Ɉڍs���Ă����B�������A�ΏƂƂ̔�r�����͑����Ȃ��B�s��Q�ւ̃��X�y���h�����^�̌������������S���Ɋւ���ő�̃f�[�^����Ă��邪�A1�N�ԂɌ����Ă���B��蒷���̈��S�����������Ƃ�����̉ۑ�ł���B
| �@�@ |
| |
|

|
Copyright
 2002-3 by DOL Inc. All rights reserved.
2002-3 by DOL Inc. All rights reserved. |
|
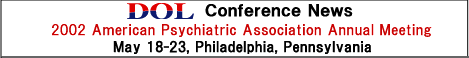 �@�@�@�@
�@�@�@�@