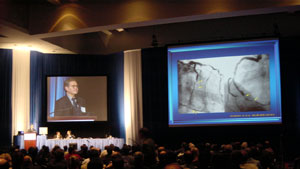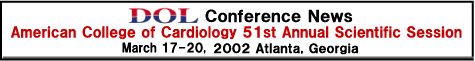 DOL ACC 2002 学会速報 |
|
|
| 冠動脈疾患 Coronary Artery Disease |
|
|||||||||
| Late-Breaking Clinical Trials I | |
| 急性冠症候群患者の虚血イベント再発に対する短期アジスロマイシン治療の効果 | |
| The Effect of Short-Term Treatment with Azithromycin on Recurrent Ischemic Events in Patients with Acute Coronary Syndrome | |
|
本試験は不安定狭心症または急性心筋梗塞で入院治療を受けている患者を対象とした。アジスロマイシンによる短期の治療によって死亡や虚血イベントの発生が減少することはなかった。さらに、クラミジア肺炎病原体に対する抗体をもっていないサブグループの患者では治療の効果はみられなかった。 | |
| Controversies in Cardiology IV | |
|
ST上昇を伴わない急性心筋梗塞の治療にはアスピリンとIIb/IIIa阻害薬の併用よりアスピリンとclopidogrelのほうが優れるか | |
| Aspirin and Clopidogrel Is Better than Aspirin IIb/IIIa Inhibitor for Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome | |
|
|
|
| Protagonist:不安定狭心症でclopidogrelによる虚血イベントの再発阻止(Clopidogrel
in Unstable Angina to Prevent Recurrent Ischemic Events [CURE])試験は急性冠症候群に関して今までに行われた試験の中で最大規模のものである。この試験によって、clopidogrelは急性冠症候群を示す幅広い患者で有効であることが明確に示された。これに対して、血小板の糖蛋白IIb/IIIa阻害薬の効果は一貫性にきわめて乏しかった。急性冠症候群を有する患者であれば、誰にでもこれらの薬物のどれかを使えば有効性が示されるとは限らない。
Antagonist:急性冠症候群の患者では広い範囲にわたって早期からclopidogrelを投与したほうがよいことを裏付ける証拠がある。しかしながら、血小板糖蛋白IIb/IIIa阻害薬も救急外来でみかける特定の患者群では使用が薦められる。これらの患者群にはトロポニン陽性例や侵襲的治療が行われる患者などが含まれる。 |
|
| Late-Breaking
Clinical Trials III | |
| 冠動脈疾患を有する患者に経皮的インターベンションを行い成功した後のフルバスタチン治療の有効性に関する無作為二重盲検プラセボ対照試験:Lescol投与とインターベンションの併用による予防試験(Lescol Intervention Prevention Study [LIPS]) | |
| A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Trial of Fluvastatin after Successful Percutaneous Intervention (PCI) in Patients with Coronary Heart Disease: The Lescol Intervention Prevention Study (LIPS) | |
|
|
|
| これは過去に経皮的冠動脈インターベンションを受けた患者でスタチンによる治療を行えば、主要有害事象が減少することを示した最初の前向き試験の報告である。フルバスタチンはイベントの発生率を4年間で22%減少させた。この成績はこれらの患者で脂質を低下させる治療の重要性を支持するものである。 | |
| Acute Coronary Syndromes: Pathophysiology and New Therapies | |
| Thrombin-Inhibitors | |
| トロンビン阻害薬はトロンビンのクリスタリン構造が明らかになったことによって開発された。トロンビン阻害薬は、フィブリノーゲン外表面/ヘパリン結合部位などの活性部位に結合する。トロンビン阻害薬には1価と2価の2つのクラスがある。2価の阻害薬は出血を来しやすいという問題があるが、1価のものでは急性虚血イベントが少なく、出血の合併も減少する。1価の化合物はヘパリンより安全である。 | |
| Acute Coronary Syndromes: Treatment Decisions | |
| Non-Critical Culprit Lesion: Therapeutic Decisions | |
| 急性冠症候群に対する初期治療の後で再灌流を行う時、完全再灌流と部分的再灌流のどちらにすべきかという問題をテーマにした発表である。データによると、生存率に影響するのは再灌流が完全か不完全かということではなく、駆出率(40%以下)がより重要である。心室機能が障害されている患者では完全な再灌流が必要である。 | |
| Conservative versus Invasive Management: Long-Term Outcome | |
| 保存的治療と侵襲的治療の長所と短所が述べられた。これら2つの治療法を比較した最近の研究によって、侵襲的治療を受けた患者で、死亡、心筋梗塞、または再入院が有意に少ないことが示されてきた。この結果は最近の薬物療法の改善と技術的進歩に負うところが大きい。これらの利点を生かして薬物療法と手術療法とをうまく組み合わせることによって、急性冠動脈疾患の予後は改善してきた。 | |
| 1st Annual American College of Cardiology International Lecture | |
| Inflammation, Atherosclerosis and Acute Coronary Syndromes | |
| 動脈硬化性プラークに炎症が存在することはよく知られている。しかしながら、一般的な考えとは対照的に、冠血管の炎症は不安定狭心症や急性冠症候群とは相関するが、動脈硬化自体、あるいは虚血や心筋壊死とは相関がみられない。感染あるいは非感染的に血管の炎症を来す可能性のある多くの原因が今検討されつつある。 | |
| |
| |
| Copyright
|