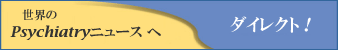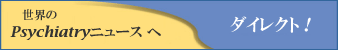| ◆ |
2つのMRIスタディによりうつ病の病態生理の理解が進みより良い治療に繋がる可能性がある [2019-12-17] |
| Two MRI studies improve understanding of the pathophysiology of depression and may lead to better treatments |
MRIがうつ病患者の脳内の異常を解明し、うつ病に対する新たなより良い治療への道を開く可能性がある、との2つのスタディ結果が2019 annual meeting of the Radiological Society of North America で発表された。1つ目のスタディでは、大うつ病性障害(MDD)において変化していることが知られている灰白質領域の血液脳関門の破壊が明らかにされた。この差は特に扁桃体および海馬において大きかった。2つ目のスタディでは、実行機能のコントロールや感情の調節に関係する脳領域の興奮や抑制が、MDD患者において低下していることを明らかにした。 |
 |
| ◆ |
低強度収束超音波は血液脳関門を開き標的薬剤を幹細胞に送達させる可能性がある [2019-12-17] |
| Low-intensity focused ultrasound can open the blood-brain barrier and allow for targeted drug and stem-cell delivery |
収束超音波は血液脳関門領域を標的とし開くために安全かつ有効な方法であり、アルツハイマー病に対する新たな治療法を可能にする、との初期研究の結果が2019 annual meeting of the Radiological Society of North America で発表された。研究者らは早期アルツハイマー病の女性3人に対し、低強度収束超音波(LIFU)を記憶に極めて重要な脳の特定部位に到達させた。治療後のMRI脳画像から、治療後すぐに標的領域の血液脳関門が開いたことを確認した。それぞれの標的領域において関門の閉鎖が24時間以内に観察された。LIFUは脳内に治療薬を供給し有効性を改善する可能性がある。 |
 |
| ◆ |
うつ病の重症度と心血管疾患との強力な関連が認められた [2019-11-19] |
| Strong link found between level of severity of depression and cardiovascular disease |
うつ病の重症度が心疾患または脳卒中の発症率を上昇させる可能性がある、との予備研究の結果が American Heart Association's Scientific Sessions 2019 で発表された。米国国民健康栄養調査(NHANES)において解答されたうつ病アンケートを用いて、うつ病と診断された成人11,000人超が同定された。そのうちの約1,200人が、心疾患または脳卒中の診断を受けている、と報告した。うつ病と非致死性心疾患および脳卒中との関連を定量化した解析によると、うつ病レベル(軽症、中等症、やや重症または重症) が上がる毎に、非致死性心疾患または脳卒中の確率が24% 上昇した。 |
 |
| ◆ |
心理的ストレスは心疾患を有する女性の重篤な心血管イベントリスクを増大させる可能性がある [2019-11-19] |
| Psychological stress may increase risk for a serious cardiovascular event in women with heart disease |
心疾患を有する女性の心理的ストレスへの反応の仕方は心筋梗塞および他の心血管イベントリスクを増大させるが、これは男性には当てはまらないようである、と American Heart Association's Scientific Sessions 2019 で発表された。ストレス反応においてIL-6バイオマーカーが1単位上昇する毎に、女性における主要な心関連イベントは41% 上昇したが、このバイオマーカーの上昇によるリスク増大は男性においては認められなかった。ストレス反応においてMCP-1バイオマーカーが10単位上昇する毎に、女性においてのみ主要な心関連イベントが13% 上昇した。 |
 |
| ◆ |
境界性パーソナリティ障害を有する中年者は心筋梗塞のリスクが高い [2019-11-05] |
| Middle-aged adults with borderline personality disorder at higher risk for myocardial infarction |
境界性パーソナリティ障害の症状を有する中年者は、これを有さない他の中年者よりも心血管系悪化の身体的徴候を有することから、心筋梗塞のリスクが高い可能性がある、と Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment に掲載された。研究者らは、参加者1,295人が自己申告の基本的人格特性および抑うつ症状を観察した健康データを解析した。いくつかの身体的健康測定値を組み合わせることにより、各参加者の相対的心血管疾患リスクスコアも確立した。境界性パーソナリティ障害の特性および抑うつのいずれもが心血管疾患リスクと有意に関連があったが、境界性パーソナリティ障害の特性の影響は、うつ症状とは関連がなかった。 |
 |
| ◆ |
臭いの識別と認知機能スクリーニングを組み合わせることでアルツハイマー病への移行がないことを予測する [2019-11-05] |
| Cognitive screen paired with odor identification predicts lack of transition to Alzheimer's disease |
認知機能および臭いを見極める能力を測定する2つの短時間検査において成績が良好であることは、アルツハイマー病の発症リスクが非常に低いことを示す、と Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association に掲載された。研究者らは、短時間の認知機能スクリーニング検査および40項目の臭い識別検査を受けた、認知症を有さない軽度認知機能障害高齢者749人のデータを解析した。4年間の追跡期間中、参加者のうち109人が認知症を発症し、その大多数がアルツハイマー病と診断された。軽度の記憶障害を有し両方の検査成績が良好であった患者のほぼ全員(96.5%)は、スタディ期間中には認知症を発症しなかった。 |
 |
| ◆ |
スタディの結果、若年成人期の外傷後ストレス障害と中年期の脳卒中リスクとの関連が示された [2019-10-29] |
| Study demonstrates link between trauma-induced stress disorders and risk of stroke in young and middle-age adults |
心的外傷後ストレス障害(PTSD)に罹患した若年成人は中年期までに一過性脳虚血発作(TIA)または重症脳卒中イベントを発現する可能性が高く、よく知られたリスクファクター以上にリスクを上昇させる、と Stroke に掲載された。イラクやアフガニスタンに従軍していた米国の退役軍人は、TIA 発症率が2倍高く、脳卒中発症率が62% 高かった。複数の脳卒中リスクファクター、併存する精神疾患、および薬物やアルコールの乱用で補正後、PTSD を有する退役軍人はPTSD を有さない退役軍人に比べ、TIA および脳卒中発症率がそれぞれ61% および36% 高かった。 |
 |
| ◆ |
頻繁な飲酒はむちゃ飲みよりも心房細動の強力なリスクファクターである [2019-10-29] |
| Frequent drinking is greater risk factor for atrial fibrillation than binge drinking |
頻繁な少量飲酒は、むちゃ飲みよりも心房細動の発症率を上昇させるようである、と EP Europace に掲載された。週当たりの飲酒の回数は、年齢や性別に関係なく新規発症心房細動の最強のリスクファクターであった。週2回の飲酒(対照群)と比較し、毎日の飲酒はリスクが最大(ハザード比[HR]1.42)であり、週1回の飲酒はリスクが最小(HR0.933)であった。少量飲酒者と比較し、飲酒をしない者、中等度の飲酒者、または大量飲酒者のリスクはそれぞれ、8.6%、7.7%、および21.5% 上昇した。むちゃ飲みは新規発症心房細動とは明らかな相関を示さなかった。 |
 |
| ◆ |
エストロゲン曝露期間の延長および長期ホルモン療法の認知機能低下治療における恩恵 [2019-10-23] |
| Benefits of extended estrogen exposure and longer-term hormone therapy in treating cognitive decline |
Menopause オンライン版に掲載された研究の結果、ホルモン療法による長期の生殖補助医療による認知面の有益性が示唆された。研究者らは閉経後女性2,000人超を12年間追跡し、エストロゲンと認知機能低下との関連を調査した。エストロゲン曝露期間が長いことは、認知機能状態が良好であることと関連があった。さらに、これらの有益な効果は、参加者の中で特に最高齢の女性群において、ホルモン療法を用いることにより拡大された。ホルモン療法を早くに開始した女性ほど、ホルモン療法開始が遅かった女性に比べ、認知機能検査の点数が高く、ホルモン療法に重要な意味をもつ期間についての仮説を支持している。 |
 |
| ◆ |
認知症における攻撃性および興奮は薬物を用いることなく良好に治療できる [2019-10-23] |
| Aggressive and agitated behaviors in dementia are better treated without medications |
認知症患者の攻撃性や興奮を軽減するために、マッサージやタッチ療法などの非薬物療法は薬物療法よりも有効なようである、との系統的レビューおよびメタ解析の結果が Annals of Internal Medicine に掲載された。5つの評価項目において、集学的治療、マッサージおよびタッチ療法、音楽療法、音楽とマッサージおよびタッチ療法の併用、および認知刺激療法は、薬物療法に比べ臨床的に有効であった。サブグループ解析において、一部の薬物療法(デキストロメトルファン‐キニジンおよび大麻類)はプラセボまたは通常治療よりも有効であったが、一部の薬物療法の有害性は知られていることから、非薬物療法が優先されるべきである、と筆者らは述べている。 |
 |