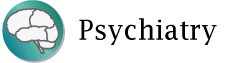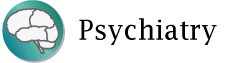| ◆ |
貧血は従来の心血管リスクファクターと関係なく軽度認知機能障害と関連がある [2015-12-28] |
| Anemia associated with increased risk of mild cognitive impairment independent of traditional cardiovascular risk factors |
ドイツにおいてランダムに選択された参加者を対象とした大規模な地域住民ベースのスタディの結果、男性で<13g/dlおよび女性で<12g/dlのヘモグロビン濃度で定義した貧血対象者は言語記憶や実行機能の成績が低いことが示された。さらに、軽度認知機能障害(MCI)は貧血と診断された者において約2倍頻度が高かった、とJournal of Alzheimer's Diseaseに掲載された。まず、貧血を有する163人および貧血を有さない参加者3,870人について全ての認知機能サブテストの結果を比較した。貧血を有する者は心血管リスクプロファイルがより顕著であり、施行された全ての認知機能サブテスト、特に直後再生課題および言語流暢性課題において認知機能が低かった。次に、MCIと診断された579人(健忘型MCI 299人および非健忘型MCI 280人)および認知機能正常者1,438人を対象として、MCIの頻度やMCIサブタイプの診断について貧血の有無で比較した。MCIは貧血を有する者において、有さない者よりも2倍頻度が高かった。同様の結果がMCIサブタイプにおいても認められ、低ヘモグロビン値は異なる経路を介して認知機能を低下させる可能性のあることが示唆された。 |
 |
| ◆ |
SSRIおよびvenlafaxineは躁病リスクおよび双極性障害リスク上昇と関連する [2015-12-28] |
| SSRIs and venlafaxine linked to heightened risk of mania and bipolar disorder |
うつ病に対しある種の抗うつ薬を服用することはその後の躁病および双極性障害リスク上昇と関連がある、とオンライン誌BMJ Openに掲載された。この結果は、単極性うつ病のレセプトにおける21,000人余りの成人の匿名化された医療記録を基にした。2006〜2013年の躁病および双極性障害診断リスクは全体で年当たり1.1%(10.9/1,000人年)であった。診断の最多年齢は26〜35歳であり、これらの患者では年当たりのリスクが1.2%(12.3/1,000人年)であった。最も多く処方された抗うつ薬はSSRI(35.5%);ミルタザピン(9.4%)、venlafaxine(5.6%)、三環系抗うつ薬(4.7%)であった。過去の何らかの抗うつ薬による治療はその後に双極性障害および/または躁病と診断されるリスクが高いことと関連があり、その年当たりのリスクは1.3〜1.9%(13.1〜19.1/1000人年)であった。さらに解析した結果、このリスク上昇は特に、選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)および二重作用抗うつ薬venlafaxineによる治療と関連があることが示された。これらの薬剤は双極性障害および/または躁病と診断されるリスクを34〜35%上昇させた。これらの結果は可能性のある影響因子を考慮に入れても当てはまった。 |
 |
| ◆ |
小児早期のうつ病と灰白質の発育に関連が認められた [2015-12-22] |
| Association found between early childhood depression and cortical gray matter development |
就学前にうつ病を発症した小児の脳は、うつ病を発症していない就学前児の大脳皮質に比べ発育が異常である、とJAMA Psychiatryに掲載された。研究者らは193人の小児を調査したが、うち90人は就学前にうつ病と診断されていた。臨床評価を行い6〜8歳および12〜15歳の間の3時点においてMRI検査を施行した。スタディ対象の小児計116人が3回の脳画像検査全てを受けた。小児が正常に発育する場合、思春期までは灰白質はますます増加するが、その後刈り込みと呼ばれる処理が始まり、不必要な細胞は死滅する。しかし今回のスタディでは、うつ病小児においては刈り込みによると思われる大幅な細胞減少が示された。さらに、脳組織の容積や厚みの減少の急激さは、うつ病の重症度と相関があった。うつ病が重篤な小児ほど、脳の容積や厚みの減少度が大であった。興味深いことに、灰白質の容積と厚みの差は、感情に関係する他の脳部位の差よりもより顕著であった。 |
 |
| ◆ |
アルツハイマー病を検出する自動化技術を用いて4つの言語的要素間の相互作用が評価される [2015-12-22] |
| Scientists evaluate interplay between four linguistic factors using automated technology to detect Alzheimer's disease |
4つの言語的要素間の相互作用を評価しこれらの障害を検出する自動化技術を開発することにより、82%以上の精度でアルツハイマー病を診断する方法が見いだされた。このスタディはJournal of Alzheimer's Disease 12月号に掲載された。研究者らはアルツハイマー病の可能性があるかまたは可能性が高いと診断された患者とコントロール97人のデータベースのスピーチサンプル(オーディオファイルを含む)を評価した。その後、自動検出アルゴリズムを用いてアルツハイマー病患者の経験した言語障害の多様性を明らかにした。彼らは、4つの総合的な発話の特徴(過度に簡単な単語を用いるなどの意味的障害;ゆっくり話すなどの聴覚障害;より単純な文法を用いる文法障害;および写真の主な様相を明瞭に同定できないなどの情報障害)が認知症を示唆すると結論付けた。この解析をより正確にしているのは、ソフトウエアを用いて、裏面では、詳細かつ自動的に検出された多数の項目を計測しているからである、と筆者らは示唆している。この技術の利点は、繰り返し利用可能であり個体間に起こり得る知覚の差やバイアスなどの影響を受けないことである。 |
 |
| ◆ |
脳のグルタミン酸経路を標的とした薬物は早期の統合失調症患者に有効である [2015-12-15] |
| Drug targeting brain's glutamate pathway effective for schizophrenia patients early in their disease |
ポマグルメタッドメチオニルと呼ばれる化合物は全ての患者に有効ではないが、統合失調症の早期または第2世代抗精神病薬や他のセロトニン-2受容体拮抗薬を用いた広範な前治療歴のない患者に、有用な可能性がある。脳のグルタミン酸経路の障害が統合失調症の症状に影響することを示すエビデンスが増加していることから、グルタミン酸経路は多くの新薬治療の標的となっている。Biological Psychiatryに掲載された研究結果から、少なくともこれらの薬剤の1つは早期の統合失調症患者に有効な可能性がある。ポマグルメタッドメチオニルの臨床試験で結論が出せなかったものを再解析した結果、より照準を絞った対象‐早期の患者または他の抗精神病薬への曝露歴のない患者‐においては統計学的に有意な反応が認められる可能性のあることが示唆された。今回のスタディの筆者らは、これらの過去のトライアルは薬物に反応しない対象を無頓着に選択している可能性があり、今後の有効性トライアルは患者のサブグループの同定が必要である、との仮説を立てている。 |
 |
| ◆ |
前立腺がんに対するテストステロン低下療法はアルツハイマー病リスクを上昇させる可能性がある [2015-12-15] |
| Testosterone-lowering therapy for prostate cancer may increase risk of Alzheimer's disease |
前立腺がんに対しアンドロゲン遮断療法(ADT)を施行されている男性が、追跡数年後にアルツハイマー病と診断される確率がこの治療を施行されなかった患者の約2倍である、との医療記録の解析結果がJournal of Clinical Oncologyに掲載された。研究者らは約500万人の患者を含む大規模な二組の医療記録を評価した。うち16,888人が前立腺がんと診断され他の全てのスタディのクライテリアに合致した。これらの患者のうち2,400人がADTを受け、追跡を必要とされた。2つの異なる統計的解析法を用いて研究チームは、ADT群はコントロール群に比べ初回のアンドロゲン低下療法後数年以内にアルツハイマー病と診断される数が有意に多いことを示した。最も洗練された測定法によると、ADT群患者は追跡期間中にアルツハイマーと診断される確率が約88%高かった。またこの解析から"用量反応効果"も示唆された。ADTを長く施行されている者ほどアルツハイマー病リスクが高かった。また、ADT療法期間が長い患者のアルツハイマー病リスクは、ADT療法を受けていないコントロールの2倍以上であった。 |
 |
| ◆ |
インターベンショナルラジオロジーを施行中の患者の否定的な感情は転帰に影響し得る [2015-12-08] |
| Patient's negative feelings during interventional radiology procedure can affect outcome |
血管形成術またはその他のインターベンショナルラジオロジーの施行前に、高度の苦悩、恐怖および敵意の感情は転帰不良につながる可能性がある、と2015年Radiological Society of North America年次集会で発表された。研究者らは、血管および腎臓インターベンションなどの画像誘導下インターベンショナルラジオロジーを施行された女性120人および男性110人計230人(平均年齢55歳)を解析した。患者は、強気、キビキビとしている、決断力がある、およびその他の肯定的な感情、さらに罪悪感、緊張感または怒りっぽさなどの否定的な感情をどの程度有しているかを5点満点の評価尺度を用いて報告した。患者は肯定的な感情の高スコアおよび低スコアと、否定的な感情の高スコアと低スコアに基づきグループ分けされた。これらのグループは、施術中の遷延性低酸素症、高血圧、低血圧、術後出血または徐脈などの有害事象発現と関連した。否定的な感情が高スコアの患者104人のうち、23人(22%)が有害事象を発現したのに対し、低スコアの患者126人では15人(12%)であった(p=0.04)。肯定的な感情の度合いは有害事象発現率に有意な差をもたらさなかった。 |
 |
| ◆ |
若年成人期の座位行動やテレビの長時間視聴は中年期の認知機能に影響する可能性がある [2015-12-08] |
| Sedentary behavior and high levels of television viewing during young adulthood affects cognitive performance in midlife |
若年成人期にテレビを長時間視聴し身体活動レベルが低いことは25年後の中年期の認知機能不良と関連がある、とJAMA Psychiatryに掲載された。成人3,247人(18〜30歳)を対象とした今回のスタディでは、テレビ視聴および身体活動を評価するアンケートを25年間にわたる受診の際に繰り返し行った。テレビの長時間視聴は、受診時の3分の2以上においてTVを1日当たり3時間以上視聴すると回答することで定義され、運動は時間と強度に基づく単位で計測された。認知機能は、処理速度、実行機能および言語記憶を判断する3つの検査を用いて25年後に評価された。25年間テレビを長時間視聴した参加者353人(3,247人中10.9%)は、いくつかの検査において認知機能不良の傾向が強かった。25年間の身体活動が低かった528人(16.3%)は、1つの検査で成績不良であった。テレビの長時間視聴と身体活動レベルが低かった107人(3.3%)は、認知機能が低い割合が約2倍高かった。 |
 |
| ◆ |
長期間にわたり親族に世話をされた小児の灰白質が大きいことがMRIにより示された [2015-12-01] |
| MRI reveals larger gray matter volumes in children left in care of relatives for extended periods of time |
長期にわたり親の直接的な世話が得られない状態であった小児の灰白質容積が大きいことが示された、と2015年Radiological Society of North America年次集会で発表された。世界中で、政治的混乱、経済的必要性または他の理由により、親は時に数か月または数年間にわたり子供を置いて家を離れざるを得ない。親に置いて行かれた女児および男児(7〜13歳)38人のMRI所見が親と共に生活しているコントロールの女児および男児(7〜14歳)のMRI所見と比較された。その後、研究者らはそれぞれの参加者群における知能指数(IQ)を計測し、認知機能を評価した。その結果、置いて行かれた小児においては親と共に生活している小児に比べ、複数の脳領域、特に感情の脳回路において灰白質容積が大きいことが明らかにされた。記憶の暗号化や回復に関連する灰白質容積はIQと反比例した。灰白質容積は脳の刈り込みおよび成熟が不十分であることを反映する可能性があり、灰白質容積とIQスコアとの反比例は、親によるケアがない状態での成長は脳の発育を遅延させる可能性があることを示唆する。 |
 |
| ◆ |
機能的MRI検査の結果、肥満は神経学的障害の側面を有していることが示された [2015-12-01] |
| Functional MRI exams show obesity has a neurological disorder component |
肥満小児が食物の匂いに出くわすと衝撃性や強迫性障害の発症に関連する脳領域が活性化される、と2015年Radiological Society of North America年次集会で発表された。研究者らは30人の小児(6〜10歳)を調査した。これらの小児のうち半数はボディーマスインデックス(BMI)が19〜24と正常であった。その他の半数はBMIが30を超えていた。各小児に対し3つの匂い標本(チョコレート、玉ねぎおよびアセトンを希釈したニュートラルな匂い)が提示された。参加者が標本の匂いを嗅いでいる時に2つのMRI技術‐機能的MRI(fMRI)および機能的結合MRI(fcMRI)‐を用いて脳活性度が計測された。食物の匂いは、肥満小児において衝撃性や強迫性障害の発症に関連する脳領域の活性化のきっかけとなったが、衝撃性コントロールに関連した脳領域においては活性化が示されなかった。しかしBMIが正常な小児においては、快楽制御、組織および計画、そして感情処理または記憶機能の管理領域がより活性化した。 |
 |