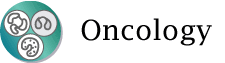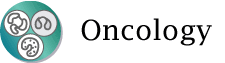| ◆ |
HER2陽性乳がん患者に対する有効性の高い治療オプションが同定された [2013-12-24] |
| Highly effective treatment option identified for patients with HER2-positive breast cancer |
化学治療薬ドセタキセルおよびカルボプラチンとHER2標的療法トラスツズマブの併用は、腫瘍サイズやリンパ節転移の有無にかかわらず、HER2陽性乳がん患者の理想的な術後治療オプションであることが確認されたとのBETHスタディの結果が2013年サンアントニオ乳がんシンポジウムで発表された。この第III相スタディでは3,509人の患者を組み入れ、3,231人はTCH(ドセタキセル、カルボプラチンにトラスツズマブ併用)またはTCHとベバシズマブの群に無作為に割り付けられた(コホート1)。コホート2は、トラスツズマブに加えアントラサイクリンエピルビシンを用いたアントラサイクリンベースの治療にベバシズマブを加えるかまたは加えない群に無作為に割り付けられた患者278人が含まれた。追跡期間中央値38か月後の無病生存期間は、TCHコホートでは両群ともに92%であり、コホート2のコントロール群では89%弱であった。この差は統計学的に有意ではなかった。さらに、HER2陽性乳がんに対する術後補助療法にベバシズマブを追加することによる有益性は認められなかった。これらの結果は、HER2陽性乳がん患者においては、例え腫瘍が大きかったりリンパ節陽性であったりしても、理想的な結果を得るためにアントラサイクリンを治療の一部に含めることは不要であることを示している。 |
 |
| ◆ |
アロマターゼ阻害薬を内服している乳がんサバイバーにおける関節痛は運動で改善する [2013-12-24] |
| Joint pain decreased with exercise in breast cancer survivors taking aromatase inhibitors |
アナストロゾール、レトロゾール、エキセメスタンなどのアロマターゼ阻害薬(AIs)を内服している乳がんサバイバーは、内服中に運動をすることにより関節痛が軽減した、と2013年サンアントニオ乳がんシンポジウムで発表された。121人のスタディ参加者は、stage 1〜3のホルモン受容体陽性乳がん患者でAIを内服している閉経後女性であった。全員が軽度以上の関節痛を有しており、組み入れ時には全く運動を行っていなかった。最悪の疼痛、疼痛重症度、および痛み介入の計測値は運動療法群に振り分けられた患者において20%低下したのに対し、通常ケア群においては、関節痛は増悪したかまたは変化がなかった。運動を行った者は、年齢、疾患stage、化学療法、放射線療法、またはその両者のいずれを受けているか、またはAI内服期間に関係なく改善した。監視下運動療法に80%以上参加した患者は最悪疼痛スコアが25%低下したのに対し、参加が80%未満であった者では14%であった。心肺機能の健康状態が5%上昇した女性は最悪疼痛スコアが29%低下したのに対し、心肺機能健康度の改善がそれより少ない者では7%の低下であった。 |
 |
| ◆ |
MRガイド下高度集束超音波により非侵襲的乳がん焼灼が確実に施行できる [2013-12-17] |
| MR-guided high intensity focused ultrasound offers reliable ablation of invasive breast cancer |
磁器共鳴(MR)ガイド下で集束超音波機器を用いた技術により腫瘍を熱し破壊することにより乳がんが安全かつ有効に治療できるとの研究結果が、Radiological Society of North America(RSNA)年次集会で発表された。MRガイド下集束超音波機器(MRgFUS)アブレーションは高度集束超音波の音響エネルギーを用いて病的組織を焼灼する非侵襲技術である。病変部位の特定およびアブレーション中の温度変化のモニターのためにMRIを継続的に使用する。研究者らは、浸潤性乳管がん患者12人において、がんの外科的切除およびリンパ節生検の前にMRgFUSを施行し、安全性および有効性を評価した。彼らは3T MRIを用いて、がん病変部位が存在し治療可能であることを確認した。その後患者らに単回のMRgFUS治療を施行した。研究者らは術後病理所見により治療の有効性を評価した。施術中または施術直後に有意な合併症を来した患者はいなかった。患者12人中10人においては、施術後に治療領域にMRI上強調される部位は認められなかった。これらの10人の患者においては、術後の組織評価により治療領域に残存病変はないことが確認された。 |
 |
| ◆ |
スクリーニングのマンモグラフィーを頻回に受けていた患者ほどリンパ節転移陽性率が有意に低かった [2013-12-17] |
| Patients who had screening mammograms more often had a significantly lower rate of lymph node positivity |
スクリーニングマンモグラフィーにより検出された乳がん患者を対象としたスタディにおいて、スクリーニングマンモグラフィーをより頻回に受けていた患者はスクリーニング検査間隔が長期であった患者よりもリンパ節転移陽性率が有意に低かったとの結果であった、と2013年Radiological Society of North America年次集会で発表された。この後ろ向きスタディは、スクリーニングマンモグラフィーで乳がんを発見された女性332人を対象とし、スクリーニングマンモグラフィーの間隔に基づき3群(1.5年未満、1.5〜3年、3年以上)のうちの1つに割り付けられた。女性の数はそれぞれ207、73および52人であった。年齢、乳房密度、高リスク状況および乳がん家族歴などで補正した結果、スクリーニングの間隔が1.5年未満の女性はリンパ節転移陽性率が8.7%と最低であった。リンパ節転移陽性率は1.5〜3年および3年以上の群でそれぞれ20.5%および15.4%で有意に高かった。これらの結果に基づき筆者らは、女性らは40歳時にスクリーニングマンモグラフィーを開始し、2年に1度ではなく毎年受けるべきであると述べている。 |
 |
| ◆ |
デジタル乳房トモシンセシスを用いることによりがん検出目的の再検査率が有意に改善した [2013-12-10] |
| Ratio of callback to cancer detection rate improved significantly when using digital breast tomosynthesis |
大規模乳がんスクリーニングプログラムにおいてデジタル乳房トモシンセシス(DBT)は再検査率を減少させがん検出率を上昇させた、と2013年Radiological Society of North America年次集会で発表された。デジタル乳房トモシンセシスは、若年女性およびデンスブレストの女性を含む全ての群の患者における再検査率軽減において有望であることが示された。トモシンセシスは電離放射線を用いて乳房の画像を作成する点においてマンモグラフィーと類似である。しかし、従来のマンモグラフィーとは異なり、トモシンセシスは乳房組織の3次元再構築をすることにより乳房全体を連続したスライスで観察することが可能である。スタディにおいて研究者らは、2011年以降にDBTを施行された女性15,633人の画像結果とその前年にデジタルマンモグラフィー検査を施行された患者10,753人の画像を比較した。デジタルマンモグラフィーと比較し、平均再検査率はDBTを用いることにより10.40%から8.78%まで低下し、がん検出率は4.28%から5.25%(患者1,000人当たり)に上昇した。全体の陽性的中率は4.1%からDBTを用いることにより6.0%に上昇した。トモシンセシスは進化しているプラットフォームであり、将来この技術はさらに向上するであろう、と研究者らは強調している。 |
 |
| ◆ |
一部の女性における加齢に伴う乳房密度の変化率が乳がんリスクに影響する可能性がある [2013-12-10] |
| The rate at which breast density changes in some women as they age may affect their breast cancer risk |
若年女性において自動乳房密度測定は乳がんリスクの予測因子であり、一部の女性においてリスクは加齢に伴う乳房密度の変化率に関連するとの研究結果が2013年Radiological Society of North America年次集会で発表された。研究者らは若年女性と高齢女性の乳房密度とがんリスクを比較し、リスクが経時的な乳房密度変化にどのように関連するかを解析した。スタディ対象は乳がん282症例および健康なコントロール317人であり、フルフィールドデジタルマンモグラフィーを施行され、乳房密度は自動ボルメトリックシステムを用いて別に測定された。したがって、再現性のある客観的な定量的密度計測を行うことができた。乳がん患者は最高50歳の健康な参加者よりもマンモグラフィー上の密度が高かった。健康なコントロールは乳房密度が年齢とともに直線的に有意に低下したが、乳がん患者では乳房密度の減少にかなりばらつきがあった。マンモグラフィー上乳房組織密度が高い女性に関してはより短い間隔で追跡し、MRIや超音波などの他の画像も用いてがんの早期発見および治療を行うことが望ましい、と筆者らは述べている。 |
 |