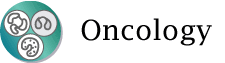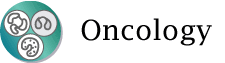| �� |
BI-RADS 3�a�ς�6������ɋ^�킵���ω�������m�����Ⴂ���Ƃ���N1��̌o�ߊώ@���K�ł��邱�Ƃ����������@[2013-08-27] |
| Low rate of suspicious changes of BI-RADS 3 lesions at 6 months suggests that yearly follow-up may be appropriate |
2,600�l�ȏ�̏�����ΏۂƂ������{�݉摜�g���C�A���̃f�[�^�Ɋ�Â��A�lj��̒����g�X�N���[�j���O�����ɂ�����'�ǐ��ł���\��������'�ƕ��ނ��ꂽ���[�a�ς�12������i6�������ł͂Ȃ��j�̉摜�����ɂ��ĕ]���Ƃ��Ă悢�\��������A���҂̕s���A�t�H���[�A�b�v��������ѕs�K�v�Ȑ������y�����邱�Ƃ��ł���Əq�ׂ�ꂽ�B���̃X�^�f�B�̌��ʂ�Radiology�I�����C���łɌf�ڂ���Ă���B�����҂�̓g���C�A���̎Q����2,662�l�̒����g�X�N���[�j���O�����̌��ʂ���уt�H���[�A�b�v�f�[�^����͂����B2,662�l�̏����̂���519�l���v745��BI-RADS 3�a�ς�L���A����͍���̃X�^�f�B�ɂ����Ē����g�Ō��o���ꂽ�a�ϑS�̂�25%���߂��B6�Ⴊ�����ł���S�̂̈�������0.8%�ł������BBI-RADS 3�a�ςɂ����Č��o���ꂽ����̕��σT�C�Y��10mm�ł������B6�����̒ǐՊ��Ԓ��ɋ^�킵���ω����F�߂�ꂽ�̂�745��BI-RADS 3�a�ϒ��A�킸��1�ł������B12������̃t�H���[�A�b�v�摜�����̎��_�ŋ^�킵���a�ς��ʂ�BI-RADS 3�a�ϓ��ɔF�߂��A���[�O�ɂ͊g�U���Ă��Ȃ��Z����������ł��邱�Ƃ������ꂽ�BBI-RADS 3�a�ς̒ራ���������6������̃t�H���[�A�b�v�摜�����ɂ�����^�킵���ω��̊m�����Ⴂ���Ƃ��猤���҂�́A�����̕a�ςɊւ��Ă͔N1��̃t�H���[�A�b�v���K�ł���\��������Əq�ׂĂ���B |
 |
| �� |
��ᇂ̌v���ɂ��i�s�זE�x����̐��������\���ł��� [2013-08-27] |
| Tumor measurements predict survival in advanced non-small cell lung cancer |
�Ǐ��i�s�܂��͓]�ڐ��x���҂�3����2�Ɋւ��ẮA���݁A�S�������Ԃ�\������̂Ɏ�ᇃT�C�Y�͎g�p����Ă��Ȃ��BBritish Journal of Cancer�Ɍf�ڂ��ꂽ�V���ȃX�^�f�B�̌��ʁA�i�s�����X�e�[�W�ɂ����Ă��S�̂̎�ᇃT�C�Y�͐������ɑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ������ꂽ�B�����҂�́A�i�s�x����850�l�̑���ᇌa�\����ɂ͌�����ᇂ݂̂łȂ������p�߂���ё����ʂւ̓]�ڕa�ς��܂܂ꂽ�\�̋L�^���Č��������B���ς̑���ᇌa��7.5cm�ł������B����ᇌa��7.5cm�������҂̕��ϐ������Ԃ�9.5�����ł������B����ᇌa��7.5cm�����ł��������҂̕��ϐ������Ԃ�12.6�����ł���A�������Ԃ�30%���������B����ᇌa�������4���ʂɕ��ނ���ƁA�������Ԃ�8.5��������13.3�����͈̔͂ƂȂ肻�̍��͂���ɑ�ƂȂ����B�����̍��́A�N��A���ʁA���Â̎�ނȂǂ̕����̗\��\�����q����͂Ɋ܂߂Ă��ˑR�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�B���̏W�c�ɂ����Ă��m�F�����A�����̌��ʂ͍���̗Տ������⊳�҂̎��Âɉe����^����ł��낤�B |
 |
| �� |
�x�B����̕a���ɂ�������������`�Ԃ͏p��̂���Ĕ��̗\�����q�ƂȂ�\��������@[2013-08-20] |
| Micropapillary morphology in lung adenocarcinoma pathology may predict cancer recurrence after surgery |
Journal of the National Cancer Institute�Ɍf�ڂ��ꂽ�X�^�f�B�̌��ʁA�ꕔ�̔x���҂̎�ᇕa���̓���̃p�^�[���͍Ĕ��̋��͂ȗ\�����q�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B�����҂�͑����x�B����ɑ���p���{�s���ꂽ����734�l�̗Տ��I��������ѕa���������g���X�y�N�e�B�u�ɕ]�����A�����̊��҂�40%�̎�ᇂ��p�オ��Ĕ��Ƌ��͂Ɋ֘A����ُ�ȍזE�p�^�[�����������Ƃ������B���^�̑����i�K�x�B����̊��҂ɂ����邱�̕��ށi��������[MIP] �`�� �j�̗\��\���Ɋւ���L�p���������X�^�f�B�͂���܂łɂȂ��B���̌��ʁAMIP�p�^�[���̊��҂ɂ����ẮA��ᇂ��N�P�ȕ��@�Ő؏����x�@�\����������k����p�͏p��5�N�ȓ��̍Ĕ����X�N��34%�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ������ߓK�łȂ��\�������邱�Ƃ��������ꂽ�B����A�x�t�؏��p�\��ᇂƂƂ��ɔx�̍ő�3����1��؏�����W���I�Ȏ�p�@�\�̏p��5�N�ȓ��̍Ĕ����͂킸��12%�ł������B |
 |
| �� |
�X�^�f�B�̌���DNA�C���Ւf�ɂ��T�זE�}�������p�苅�������a�����Â�����@�����ꂽ [2013-08-20] |
| Study suggests way to treat T-cell acute lymphoblastic leukemia by blocking DNA repair |
Leukemia���I�����C���łɌf�ڂ��ꂽ�V���Ȍ����̌��ʁA����^�̔����a�����Âɒ�R����̂ɓ�������DNA�C�������̂̈ꕔ���Ւf���邱�Ƃɂ�艻�w�Ö@�̑t�������㏸���������Ԃ���������\�������邱�Ƃ��������ꂽ�B���̎����I���p���Ð헪�\���w�Ö@�ɉ��������q�j�Q��p����\�͓���T�זE�}�������p�苅�������a�iT-ALL�j�̗}���ɑ��L���ł������B�X�^�f�B�ł̓q�g�����a�̎��������זE������у}�E�X�̔����a���f�����g�p�����B�����҂�́A�t�@���R�j�n���iFA�j�p�X�E�F�C�̑j�Q����т����DNA�������w�Ö@��p���邱�Ƃ͗L�]�Ȃ��Ð헪�ƂȂ�Ƃ̉���̂��ƂŌ��������B�����a�זE��FA�C���p�X�E�F�C��j�Q���邽�߂ɔނ�́AmTOR�i�M���ނɂ����郉�p�}�C�V���̕W�I�j�ƌĂ��`���̑j�Q�����������B�����FANCD2�\FA�C���p�X�E�F�C�̍\���v�f�\�̗L�ӂȃ_�E�����M�����[�V�����������N�������B�Ȋw�҂�͂��̌�A���݊J���i�K�ł���3�̐V����mTOR�j�Q��ipp242�AAZD8055�����INK128�j��AraC�A�G�g�|�V�h�A����уV�X�v���`����p�������w�Ö@�ƕ��p���Ď��������BmTOR�Ɖ��w�Ö@�̕��p��mTOR�j�Q��܂��͉��w�Ö@�̒P�Ǝ��Â����͂邩�ɑt���������������B |
 |
| �� |
�������ɑ��钷���̃J���V�E���h�R��̎g�p�͓������X�N�Ɗ֘A����@[2013-08-13] |
| Long-term calcium-channel blocker use for hypertension associated with higher breast cancer risk |
���������Â̂��߂̒����J���V�E���h�R��̎g�p�͓������X�N�Ɗ֘A����Ƃ̕�JAMA Internal Medicine�Ɍf�ڂ��ꂽ�B�n��Z����ΏۂƂ������̃X�^�f�B��55�`74�̏�����g�ݓ��ꂽ�F����880�l�͐Z�������ǂ�����A1027�l�͐Z�������t�����L���A856�l�͂����L���Ȃ��R���g���[���Q�Ƃ��ꂽ�B�����҂�͓����X�N���v�����ŋ߂̍~���g�p����т��̊��Ԃ������B10�N�ȏ�J���V�E���h�R������݂������������Ă��邱�Ƃ͓��ǂ����X�N�i�I�b�Y��[OR]�A2.4�j����я��t�����X�N�iOR�A2.6�j�Ɗ֘A���������B�����̊֘A���͎g�p�����J���V�E���h�R��̌^�ɂ��傫���قȂ邱�Ƃ͂Ȃ������i�Z���ԍ�p�^�Β����ԍ�p�^�܂��̓W�q�h���s���W���n�Δ�W�q�h���s���W���n�j�B���̍~����\���A�܁Aβ�Ւf��уA���W�I�e���V���U��e�̝h�R��\�͓����X�N�㏸�Ƃ͊֘A���Ȃ������B�ߋ��ɂ������̃X�^�f�B�ɂ����ăJ���V�E���h�R��̎g�p�Ɠ����X�N�Ƃ̊֘A�����������ꂽ���A���ɒ����Ԃɂ킽�茻�݂��J���V�E���h�R��g�p���p�����Ă��邱�Ƃ������X�N�Ɗ֘A����ƔF�߂�ꂽ�̂͂��ꂪ���߂Ăł���B |
 |
| �� |
�哤�`���͈�`�q�V�O�i���`�B�o�H��}�����邱�Ƃɂ��咰�����\�h���� [2013-08-13] |
| Soy protein protects against colon cancer by repressing genetic signaling pathway |
���U�ɂ킽��哤�C�\�t���{���Q�j�X�e�C���ւ̔��I�͍זE�A�|���[�v�A����эŏI�I�ɂ͈�����ᇂ̑��B������������V�O�i����}�����邱�Ƃɂ��咰�����\�h����Ƃ̌������ʂ�Carcinogenesis�Ɍf�ڂ����B�Ȋw�҂�͔D�P���̃��b�g����т��̎e��ɑ哤�`�����o�����܂ސH������уQ�j�X�e�C�����܂ސH����^���邱�Ƃɂ�萶�U�ɂ킽��哤�ɔ��I�������B��7�T��Ƀ��b�g�̎e��͔��������ɔ��I����A���̌���哤�`���܂��̓Q�j�X�e�C���H��13�T��܂ŐH�ב������B13�T��̎��_�ŁA�p���I�ȃQ�j�X�e�C���ɔ��I���ꂽ���b�g�̑咰�O����a�ϐ���40%�������AWnt�V�O�i�����x���͐���ɂ܂Ō������Ă����B�ނ�͂܂�Wnt�V�O�i�����������I�O��Ŕ�r���A�����ꂩ�̐H�������̃A�b�v���M�����[�V�����ɉ��炩�̉e�����y�ڂ��Ă��邩���ώ@�����B�Q�j�X�e�C����H�ׂ����b�g�ɂ�����V�O�i�����O���x���͔��������𓊗^����Ă��Ȃ����b�g�Ɠ����ł������B�Q�j�X�e�C����3�̈�`�q���������������A�ُ�זE���B�₪���Ɋւ�邱���̃V�O�i�����O�ߒ���}�������B���̌��ʂ͑咰���G�s�W�F�l�e�B�b�N�Ȏ����ł��邱�Ƃ������Ă���A�ƕM�҂�͏q�ׂĂ���B |
 |
| �� |
�f�W�^���g���V���Z�V�X�͓�����X�N���[�j���O�Č������������I�Ɍ���������@[2013-08-06] |
| Digital tomosynthesis effectively reduces the recall rate in breast cancer screening |
�f�W�^���g���V���Z�V�X�͓�����X�N���[�j���O�ɂ�����Č�������ቺ������L���ȕ��@�ł��邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�Ƃ̐V���ȃX�^�f�B���ʂ�Radiology�I�����C���łɌf�ڂ��ꂽ�B�����҂��2�̃O���[�v�̏����i�]���̃f�W�^���}�����O���t�B�[�݂̂����Q�ƃ}�����O���t�B�[�ɉ����g���V���Z�V�X�����Q�j�̓�����X�N���[�j���O�Č��������r�����B�X�N���[�j���O�}�����O���t�B�[���{�s���ꂽ13,158�l��6,100�l���g���V���Z�V�X���{�s���ꂽ�B�g���V���Z�V�X���{�s���ꂽ���҂ɂ����邪�o����1,000�l������5.7�ł������̂ɑ��A�}�����O���t�B�[�P�Ƃ������҂ł�1,000�l��5.2�ł������B���Č������̓}�����O���t�B�[�P�Ƃ�12.0%�ł��������̂��g���V���Z�V�X�Q��8.4%�ł���A�g���V���Z�V�X��lj����邱�Ƃɂ��30%���������B�g���V���Z�V�X�Q�ł͂��ׂĂ̔N��Q����ѓ��B���x�ɂ����čČ������X�N�y�����F�߂�ꂽ�B�����x���[��50�Ζ����̏������g���V���Z�V�X�̉��b���ł����B�g���V���Z�V�X�̓f�W�^���}�����O���t�B�[�Ɣ�r���픘���ʂ���2�{�ł���A�L�ӂȌ��_��L����B�������A�V���ȋZ�p�ɂ��픘�ʂ͌��点��ƕM�҂�͏q�ׂĂ���B |
 |
| �� |
����̃n�C���X�N�Ɗ֘A������[�ُ̈�g�D��L���鏗���ɑ��Ă͒���I�ȉ摜�f�f�Ɛf�@�ŏ\���ȉ\�������� [2013-08-06] |
| Periodic imaging and clinical exam may be sufficient for women with a breast tissue abnormality associated with a higher risk of cancer |
����̃n�C���X�N�Ɗ֘A�������̃^�C�v�̓��[�ُ�g�D�Ɋւ��Ă͕K��������p�͕K�v�łȂ��Ƃ̐V���ȃX�^�f�B���ʂ�Radiology�I�����C���łɌf�ڂ��ꂽ�B �ٌ^���t�ߌ`���iALH�j����є�Z�������t����iLCIS�j�͓��[�����ɂ����ċ����a�ςƂ��Ď��ɔF�߂���ُ���[�a�ςł���BALH�܂���LCIS��L���鏗���͓����ǃ��X�N��4�`10�{�����B�����҂��10�N�Ԃ̕a������ѕ��ː��Ȃ̃f�[�^�����A�p��܂��͌o�ߊώ@��ɂ���ɐi�s����ALH�����LCIS�Ǘᐔ�ƕ��ː��Ȉ�ƕa����Ƃ̈�v�Ƃ̊֘A�������B���̌����ɂ��40�`73�̏���49�l��50�ǗႪ���o���ꂽ�B���ː��Ȉ�ƕa����̏�����50����43���ň�v�����B�ǐ��ň�v�����Ǘ�̂����A����ɐi�s������͈̂����Ȃ��A�����̊��҂ɂ����Čo�ߊώ@�͎�p�̑�֗Ö@�ƂȂ蓾���i�ł��邱�Ƃ����͂Ɏ������ꂽ�B��������v���Ȃ�����7��̂����A2��͔�Z�������ǂ���iDCIS�j�ɐi�s�����B�Z�J���h���C���X�N���[�j���O�@�Ƃ��ă}�����O���t�B�[�ɉ���MRI�܂��͒����g������N1��s�����Ƃŏ\���ł��낤�A�ƌ����҂�͌��_�t���Ă���B |
 |