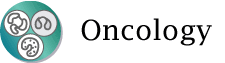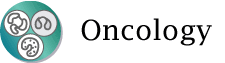| ◆ |
喫煙者は前立腺全摘術後の異常病理所見およびPSAレベル高値のリスクを上昇させる [2012-05-29] |
| Smokers at higher risk of adverse pathology findings and higher PSA levels following radical prostatectomy |
| 喫煙男性は前立腺全摘術後の異常病理所見を有する確率が高くPSAレベル上昇リスクが高いとの新たなスタディ結果が第106回American Urological Association学会で発表された。研究者らは1989〜2005年に前立腺全摘術を施行され詳細な喫煙歴の得られた男性630人を抽出した。321人が喫煙者で309人は非喫煙者であった。病理所見には前立腺重量、がん容積、高悪性度がん容積、断端の状態、精嚢転移、前立腺外進展、神経周囲浸潤、血管リンパ浸潤およびリンパ節転移の有無が含まれた。生化学的再発−前立腺全摘術後のPSAレベル上昇−はPSA 0.2ng/mlで評価された。種々の解析を用いて喫煙者と非喫煙者とを比較した。喫煙者は非喫煙者よりもがん容積が大きく(2.54対2.16mL、p=0.016)、高悪性度がん容積も大きかった(0.58vs0.28mL、p=0.004)。ヘビースモーカー(20pack×年の喫煙歴で定義)は単変量生存解析で生化学的再発のリスクが高かった;喫煙はまたCox回帰分析でも再発リスクが高いことの予測因子であり、1箱×喫煙年の喫煙歴あたりPSAレベルが約1%上昇した。 |
 |
| ◆ |
睡眠呼吸障害はがん死亡高リスクと関連がある [2012-05-29] |
| Sleep disordered breathing associated with an increased risk of cancer mortality |
| 睡眠呼吸障害(SDB)は心血管有害事象および精神病理学的予後のリスクを上昇させるが、がん死亡リスクも上昇させるとのスタディ結果が2012年American Thoracic Society International Conferenceで発表された。研究者らは、地域住民ベースの前向きスタディであるWisconsin Sleep Cohortの対象者1,522人の22年間の死亡データおよび睡眠時呼吸障害の自然経過を調査した。年齢、性別、ボディーマスインデックス、喫煙および他の因子で補正した結果、全死亡およびがん死はSDBの存在および用量−反応関係様式でSDB重症度と関連があった。SDBを有さない者と比較し、がん死亡の補正相対ハザードは軽度SDBを有する参加者で1.1、中等度SDBで2.0、そして重度SDBで4.8であった。CPAPを使用している人々(126人)を除外しても結果は同等であった。肥満の状態に基づく層別解析では、この相関は非肥満者(BMI<30kg/m2)において肥満者よりも強かった(重度閉塞性睡眠時無呼吸[OSA]対非OSAの相対ハザード比はそれぞれ6.3と3.1)。これらの結果は、中等度の低酸素が血管新生や腫瘍の成長を促進することを示した動物研究の結果と一致する。 |
 |
| ◆ |
高血圧治療目的でのβ遮断薬内服は大腸がんを予防しない [2012-05-22] |
| Taking beta blockers to treat hypertension does not protect against colorectal cancer |
| CANCER誌オンライン版に掲載された新たなスタディの結果、現在の考え方に反して、高血圧治療のためのβ遮断薬内服が大腸がん発症リスクを低下させないことが示された。長期内服やβ遮断薬のサブタイプであっても大腸がんリスクは減少させなかった。研究者らは、大腸がん患者1,762人および、がんを有さない1,708人に個人面接を行った。いくつかの患者特性(体重や喫煙の有無など)および結果に影響する可能性のある他の因子を考慮に入れた結果、β遮断薬内服と大腸がんリスクとに関連は認められなかった。過去の研究では、これらの因子は考慮されなかった。β遮断薬内服期間や特定の型のβ遮断薬、有効成分(メトプロロール、ビソプロロール、カルベジロール、およびアテノロール)、および大腸がんの発症した結腸または直腸部位により掘り下げて解析しても関連は認められなかった。この結果はまた、薬物がどのようにがんリスクに影響するかを観察したスタディの結果に影響を与える可能性のある患者特性や他の因子を考慮することの重要性をも指摘している。 |
 |
| ◆ |
新たな長期治療は幹細胞移植後の多発性骨髄腫の進行を遅延させる目的で使用しうる [2012-05-22] |
| New long-term therapy can be used after stem cell transplant to slow the progression of multiple myeloma |
| New England Journal of Medicineに掲載された新たなスタディにより、自家造血幹細胞移植後に多発性骨髄腫の進行を遅延させる目的で使用しうる新たな長期治療レナリドミドに関する有望なニュースが公表された。この第3相試験では、何か月または年単位で内服が可能なレナリドミドを用いた維持療法により、新たに骨髄腫と診断され骨髄移植を施行された患者の予後が有意に改善することを示した。3年無病生存期間(一次エンドポイント)はレナリドミド群で59%であり、それと比較しプラセボ群では35%であった。またこの薬剤により骨髄腫進行までの時間が延長し全生存期間も延長した。忍容性は良好であった。このトライアルの結果は多発性骨髄腫患者の治療を変えるであろう、と筆者らは述べている。しかし彼らは、さらにスタディを施行する必要があり、また今回のスタディの長期追跡を行いこれらの患者に対するレナリドミドの生存に関する真の有益性の有無を確認する必要があるだろうとも注記している。 |
 |
| ◆ |
乳房密度が高くても高くなくても、術前MRIはさらなる悪性腫瘍を検出するのに有益である [2012-05-15] |
| Preoperative MRI valuable in detecting additional malignancies in both dense and not dense breasts |
| 新たに乳がんと診断された患者は、たとえ高密度乳房でなくとも術前MRI検査を施行すべきであると新たなスタディにより示された。American Roentgen Ray Society Annual Meetingで発表されたこのスタディでは、さらなる悪性腫瘍および高リスク病変を検出するにあたり、高密度乳房と高密度でない乳房とで3T乳房MRIの有用性に差がないことが示された。127人の患者を対象としたこのスタディでは、3T MRIにより、高密度でないと考えられる乳房の患者の26%および高密度乳房患者の25%において悪性腫瘍が検出された。検出された病変の大きさや病変の分布に関して高密度乳房患者と高密度でない乳房の患者とで差はなかった。両群の患者ともに有意なそして統計学的に同等な割合で、反対側の乳房または同側乳房の既知のがんと異なる4分の1部位に疑われなかった新たながんを有していた。 |
 |
| ◆ |
ストラットベース乳がん放射線療法は非浸潤性乳管がん患者の治療選択を拡大する可能性がある [2012-05-15] |
| Strut-based breast cancer radiation treatment may expand treatment options for women with ductal carcinoma in situ |
| ストラットベースアプリケーターを用いた乳房小線源療法は非浸潤性乳管がん(DCIS)の治療として有効であるようであるとのスタディ結果がAmerican Society of Breast Surgeons学会で発表された。研究者らは2007〜2011年に米国内12施設でSAVI(ストラット調整ボリュームインプラント)デバイスを用いて治療された患者265人のデータを報告した。追跡期間中央値は20.1か月であり患者の年齢中央値は62歳であった。スタディ対象患者のうち14%は小線源療法アプリケーターと皮膚表面との間が狭かった(5mm以下)。このことは、このデバイスが本来6週間の乳房全照射を受けなくてはいけない皮膚に近いがんを有する女性の多くを5日間で治療することが可能であることを示している。グレード2の治療後事象を調査した結果、脂肪壊死や過剰な色素沈着は認められなかった。1.2%と低率で漿液腫、乳房痛および毛細血管拡張が認められた。このスタディは、DCIS治療のための乳房小線源療法に関する今までのスタディの中で最大のものである。 |
 |
|
◆
|
乳がんに対する腫瘤摘出後小線源療法は全乳房照射よりも合併症が多い [2012-05-08] |
| Brachytherapy associated with increased complications compared to whole-breast irradiation following lumpectomy for breast cancer |
| 浸潤性乳がんに対し乳腺腫瘤摘出術を施行された高齢女性において、小線源療法は全乳房照射(WBI)と比較し長期乳房温存の可能性が低く合併症確率が高かったが全生存率には差がなかったとのスタディ結果がJAMA 5月2日号に掲載された。この後ろ向きの地域住人を対象としたスタディでは、浸潤性乳がんに対し乳腺腫瘤摘出術を施行された女性92,735人が登録され、うち6,952人は小線源療法、85,783人はWBIでそれぞれ治療された。5年間の累積乳房切除術施行率は小線源療法群で3.95%であったのに対しWBI治療群では2.18%であり、小線源療法群においてリスクが高かった。小線源療法はまた、感染性および非感染性術後合併症リスクが高かった;1年後までに、小線源療法群の1,126人(16.20%)が皮膚または軟部組織の感染を発現したのに対し、WBI治療群では8,860人(10.33%)であった。同様に、1年後までに小線源療法群の1,132人(16.25%)が非感染性術後合併症を発現したのに対し、WBI治療群では7,721人(9.00%)であった。小線源療法は全般的に照射後合併症リスクが高かった。5年全生存率は両群間で差がなかった。 |
 |
| ◆ |
新たなバイオマーカーにより慢性リンパ球性白血病患者の予後が予測できる可能性がある [2012-05-08] |
| New biomarker may predict prognosis for patients with chronic lymphocytic leukemia |
| Gタンパク質共役型受容体(GPCR)発現により慢性リンパ球性白血病患者の予後が予測できる可能性があるとの研究結果が2012年Experimental Biology学会で発表された。GPCRは細胞外分子を感知し、パスウェイや細胞内反応を変化させる蛋白質受容体の大規模ファミリーである。特定のGPCRの発現は疾患ステージ特異的であり、CLLのバイオマーカーおよび治療標的である可能性がある。これらは細胞表面に発現し異なる組織において発現を変化させるため格好の標的である。研究者らは、GPCRの1つである血管作動性腸管ポリペプチド1型受容体(VIPR1)の発現が進行の速いCLLにおいて進行の緩徐なCLL患者における発現の700倍以上に増加しているのを発見した。さらに、VIPR1を活性化させるVIPで白血病細胞を治療すると、白血病細胞死を誘発させた。このようなGPCRはまたリンパ性白血病の原因となっている生態や病理の一部を反映しており、これらによりこの疾患の新たな治療法が得られる可能性がある。特定のGPCR発現パターンや多分独自に発現したGPCRパターンにより、他のがんや疾患を特徴付けられるかを解明するスタディが現在行われている。 |
 |
| ◆ |
化学療法および放射線療法は乳がん既往者の認知機能に影響する [2012-05-01] |
| Chemotherapy and radiation affect cognitive functioning among breast cancer survivors |
| 化学療法、放射線療法またはその両方を施行された乳がん既往者は、がんの既往のない女性と比較しいくつかの認知機能検査の成績が不良であったとのスタディ結果がCancer 4月号に掲載された。研究者らは化学療法または放射線治療施行中の早期乳がん患者313人およびがんを有さないコントロール群の女性を組み入れた。両群ともに6か月後および36か月後に検査を受けた。全ての群の参加者は年齢差が5歳以内であり、乳がん患者らと地理的に同じ地域に住むがんを有さない女性とマッチさせた。参加者は、化学療法に最も影響を受けると思われる2つの領域である処理速度と実行機能についての認知機能に関する検査を受けた。また、言語能力についても調べられた。化学療法を受けた患者は、がんを有さないコントロール群に比べ、処理速度、実行機能および言語機能検査の成績が不良であった。放射線療法群の検査成績は化学療法群のそれと同等であった。さらに、がんを有さない群の認知機能は時間とともに改善したが、化学療法群と放射線療法群では改善しなかった。放射線療法群と化学療法群の成績には差がなかった。 |
 |
| ◆ |
低侵襲前立腺摘除術は術後合併症が少なく死亡リスクが低い [2012-05-01] |
| Minimally-invasive prostate removal has fewer post-surgical complications and lower risk of death |
| 前立腺を摘出する低侵襲手術は術後合併症を軽減し輸血の必要性を少なくし退院を早める。さらに重要なことに、低侵襲手術後30日以内の死亡率は開腹術後よりも統計学的に低かったとのスタディ結果がEuropean Urology 4月号に掲載された。研究者らは、2003〜2007年に前立腺がんのために前立腺を摘除された65歳以上の男性78,232人を調査した。19,594人の男性に対し、腹腔鏡またはロボット技術を用いて低侵襲前立腺全摘除術が施行された。開腹根治的恥骨後式前立腺摘除術は58,638人に施行された。低侵襲手術に伴う合併症は経時的に減少したのに対し、従来の開腹手術合併症リスクは27.4%から32%に増加し、術後死亡は0.5%から0.8% に増加した。全体で、低侵襲手術を施行された患者の死亡リスクは0.2%であったのに対し、開腹手術を施行された患者では0.6%であった。両群とも死亡リスクは非常に低かったが、この差は統計学的に有意であり、臨床的に有意な差である可能性がある。 |
 |