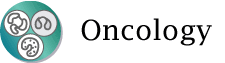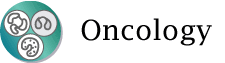|
◆ |
遺伝子プロファイリングは白血病患者の予後をより正確に予測し治療決定のガイドとなる [2012-03-27] |
| Genetic profiling can help predict prognosis more accurately and guide treatment decisions for leukemia patients |
| 急性骨髄性白血病(AML)患者の一連の遺伝子異常が同定され、医師らはこれらを用いて患者の予後をより正確に予測することが可能となり患者にとって最も有益と思われる治療を選択できるとのスタディ結果がNew England Journal of Medicine 3月22日号に掲載された。研究者らはある臨床試験に参加していたAML患者502人の血液または骨髄検体を解析した。この臨床試験では、60歳未満のAML患者における化学療法の標準用量を増加させることにより生存率が改善するか否かを調査した。研究チームは、検体を用いてAML患者において変化していることが知られている18の遺伝子の変異に関して解析した。彼らは、各々の患者の変異の存在とその患者が標準用量または高用量の化学療法のいずれかを受けることによる最終的な疾患の経過との関係について注目した。この解析により研究者らは、様々な遺伝子変異の組み合わせに特異的なリスクレベルを判断できるようになった。彼らはまた、この試験で使用された高用量化学療法が一部の患者においてのみ有益であることを立証することもできた。研究者らは現在スタディ結果を臨床応用すべく取り組んでいる。 |
|
| ◆
|
MRI灌流画像はグリオーマ患者の治療決定に有用である
[2012-03-27] |
| MRI perfusion imaging useful to aid treatment decisions for patients with gliomas |
| MRI灌流画像は、がんのマーカーである異常血管形成のエビデンスを示すことにより、成人における最も多い悪性脳腫瘍であるグリオーマが進行したかを判断する際の補助として使用可能である。American Journal of Neuroradiology 3月号に掲載されたこの前向きスタディの目的は、グリオーマ患者の治療決定においてMRI灌流画像が有用であると医師らの集学的チームが認めるか否かを明らかにすることであった。グリオーマを疑われた成人患者計59人が11か月にわたり複数のセッションで評価を受けた。従来のMRIそしてその後に従来のMRIと灌流画像検査を行い、腫瘍の状態を評価し仮の治療計画を作成した。スタディの結果、医師らの治療計画が8.5%の患者において変更され、MRI灌流画像を加えることにより治療計画の確信度が57.6%上昇した。これらの結果からMRI灌流画像は、グリオーマ患者の治療方針決定および腫瘍専門医らが治療計画を確定する過程において有意な影響を有することが示唆された。 |
|
|
◆
|
急性リンパ性白血病小児における長期生存率の安定した上昇は治療の進歩が及ぼす影響を反映している [2012-03-20] |
| Steady increases in long-term survival among children with acute lymphoblastic leukemia reflects impact of treatment advances |
| Journal of Clinical Oncology 3月12日号に掲載されたスタディの結果、小児オンコロジーグループ(Children's Oncology Group [COG])を通して治療を受けた急性リンパ性白血病(ALL)小児における5年生存率の安定した上昇が報告された。研究者らは、1990〜2005年に小児期または成人期(幼児から22歳)にALLの治療を受けた21,626人の長期生存率を解析した。これらの期間をそれぞれ同等の人数が含まれる3つの「時代」(1990〜1994年、1995〜1999年、および2000〜2005年)に分け、5年および10年生存率の経時的な変化を調査した。生存率は83.7%(1990〜1994年)から90.4%(2000〜2005年)に上昇した。生存率の改善は、年齢、性別、人種、またはALLのサブタイプに関係なく1歳以上の小児全て認められた。さらに、10年生存率は、80.1%(1990〜1994年)から83.9%(1995〜1999年)に上昇した。しかし乳児(1歳以下)においては5年生存率は1990〜1994年(52.1%)と2000〜2005年(50.3%)とでほとんど変化がなく、一方、死亡原因は大きく変化した。ALL再発または進行は1990〜1994年の43%から2000〜2005年の27.2%に減少したが、治療関連死はこの期間に3.9%から13.9%に上昇した。 |
|
| ◆
|
男性の初回性交前に包皮環状切除を行うことにより前立腺がんリスクが減少する
[2012-03-20] |
| Circumcision before male’s first sexual intercourse reduces risk of prostate cancer |
| Cancerオンライン版に掲載された新たな解析の結果、男性の初回性交前の包皮環状切除は前立腺がん予防に役立つ可能性があることが報告された。研究者らは3,399人の男性(前立腺がんを有する者1,754人および前立腺がんを有さない者1,645人)の情報を解析した。初回の性交前に包皮環状切除された男性は包皮環状切除を行われていない男性と比較し、前立腺がん発症率が15%低かった。このリスク低下は悪性度の低いがんおよび悪性度の高いがんいずれにおいても認められた。特に、初回の性交前に包皮環状切除された男性は悪性度の低い前立腺がん発症リスクが12%低く、悪性度の高い前立腺がん発症リスクが18%低かった。今回のスタディの結果、包皮環状切除によりがんの誘引となる感染症や炎症が妨げられる可能性があることが示唆された。性感染症は、がん細胞にとって快適な環境を作り出すことにより慢性炎症を引き起こし前立腺がん発症につながる可能性がある。他のメカニズムもまた関与している可能性もある。包皮環状切除は内部包皮を頑健にし包皮下の病原菌の生存を助長する湿った空間を除去することにより性感染症を予防しその結果、前立腺がんを予防する可能性がある。 |
|
| ◆
|
HPV関連の中咽頭がん治療において経口ロボット手術は成功率が高くより非侵襲的であることが示された [2012-03-13] |
| Transoral robotic surgery proves successful, less invasive way to treat HPV-related oropharyngeal cancer |
| 経口で施行されるロボット手術は咽喉背部の特にHPV陽性患者の扁平上皮がん切除において非常に優れた結果を示したとのスタディ結果がMayo Clinic Proceedings 3月号に掲載された。研究者らは、中咽頭がんに対しda Vinciロボット手術システムを用いた経口ロボット手術を施行された患者66人を追跡した。数か月ごとに患者は画像検査や診察を受けがん再発の有無を確認された。2年後の患者の生存率は92%を超え、中咽頭がんに対する他の手術や手術以外の治療による生存率と同等であった。従来の咽喉腫瘍切除術は下顎骨、頚部、舌などを切除し再建する必要があり侵襲の大きなものであったため、研究者らはロボット手術後の患者の治癒に関しても関心をもっていた。経口ロボット手術後患者の96%が術後3週以内に常食を嚥下することができた。胃瘻造設チューブを必要としたのは4%未満であった。複数の病院を組み入れた延長研究が計画されており、さらに多くの中咽頭がん患者に対する経口ロボット手術が調査される予定である。 |
|
| ◆ |
乳房痛の評価においては標準的な乳房の診察に画像検査を追加しても有益性は少ない [2012-03-13] |
| Little benefit seen from adding imaging studies to normal breast examination for breast pain evaluation |
| 乳房痛の評価の一部として画像検査(マンモグラフィー、MRIまたは超音波)を受け、フォローアップ診断検査を受けてもこれらの追加検査による有益性は得られないとのスタディ結果がJournal of General Internal Medicine オンライン版に掲載される。研究者らは2006〜2009に乳房痛で受診した女性群916人を解析した。彼らは、乳房痛の評価のために画像検査を受けた女性と受けなかった女性の臨床上の管理について比較した。6件のがんが検出された:これらの女性は全員診察でしこりが認められたか、またはルーチンのスクリーニングマンモグラフィーによりもう片方の乳房のがんが発見されたものであった。診察上全く正常であった女性においては追加の超音波検査、MRIまたはマンモグラフィーは乳房痛の原因確定には役立たなかった。標準的なスクリーニングを超えた追加の超音波検査や他の検査は、さらに医師の診察を受けたり余計なマンモグラフィーや生検などを受けたりする好ましくない側面もある。 |
|
| ◆ |
大腸内視鏡スクリーニング検査中に腺腫性ポリープを切除することにより大腸がんによる死亡リスクが軽減する [2012-03-06] |
| Removing adenomatous polyps during colonoscopy screening reduces risk of death from colon cancer |
| 大腸内視鏡によるポリープ切除は大腸がん発症を予防するのみならず大腸がん死も予防するとのスタディ結果がThe New England Journal of Medicine 2012年2月23日号に掲載された。腺腫性ポリープは大腸内視鏡検査で最も多く発見される異常所見であり、がん化する可能性がある。過去の研究の結果これらのポリープを切除することによりがんを予防できることが示されているが、予防されたがんが致死的である可能性があるか否かについては明らかにされていなかった。研究者らは国内ポリープスタディ National Polyp Study((NPS、この種のスタディで最大)に組み入れられた患者2,602人の長期結果を評価した。その結果、これらの病変を検出し切除することにより、同等の人口、年齢および性別の一般人口において予測される大腸がん死亡率と比較し53%低下することが示された。さらに、腺腫性ポリープを切除された患者の大腸がん死亡率は、切除後最長10年間はこれらのポリープを検出されなかった人々と同様に低かった。 |
|
| ◆ |
VEGFおよびc-METの両者の阻害は膵神経内分泌腫瘍の浸潤および転移を阻害する [2012-03-06] |
| Dual inhibition of VEGF and c-MET inhibits tumor invasion and metastasis in pancreatic neuroendocrine cancer |
| 血管内皮細胞増殖因子(VEGF)およびc-METシグナリングの両者の阻害は膵神経内分泌腫瘍の浸潤および転移を阻害するとの論文が、American Association for Cancer Researchの最新学会誌Cancer Discoveryに掲載された。過去の実験結果では、ベバシズマブやスニチニブのような薬剤でVEGFシグナリングを阻害することにより、腫瘍浸潤や転移を増強するなどの多くの副作用が発現する可能性があった。不明であったのは、抗VEGF療法により、腫瘍細胞の浸潤や転移を促進することが報告されているc-MET上昇を引き起こすかどうかであった。これを明らかにするために研究者らは、2段階の実験を行った。膵神経内分泌腫瘍を発現するように操作されたマウスを抗VEGF抗体で治療したところ、腫瘍サイズは縮小したが浸潤性および転移性は上昇した。この治療によりまた腫瘍の低酸素および発現そしてc-MET活性が増加した。しかし、VEGFおよびc-METシグナリングを同時に阻害すると浸潤および転移も軽減した。研究者らは3つのc-MET阻害薬(crizotinib およびc-METを標的とするがVEGFシグナリングは標的としない PF-04217903、およびVEGFとc-METシグナリングの両者を遮断するデュアル阻害薬cabozantinib)を試みた。 |
 |