|
心不全治療の究極の目的は患者の生命を延長させることにある。左室機能障害を有する患者は、心不全の徴候や症状の有無にかかわらず通常心不全の進行(ポンプ機能不全の増悪)または心臓突然死(通常は心室性不整脈)で死亡する。
左室機能障害または心不全の予後を改善するためには、上記2つの死因に関する有病率と死亡率を減少させる必要がある。臨床試験のデータにより心臓再同期療法(CRT)は生命予後を改善することが示されているが、エビデンスの重さからは、CRTはポンプ機能不全の増悪による死亡は減少させるが心臓突然死は減少させないことが示唆される。
再同期療法の臨床試験では、生活の質、機能分類、運動耐容能、リモデリングの指標、および有病率と死亡率等の、多くの指標が評価された。
全部で4,000例以上の患者を対象にした12以上の試験でCRTは例外なく生活の質と機能分類の程度を改善した。どのデータも驚くほど一致しており、Minnesota
Living with Heart Failure quality of life score(心不全と共に生活する上で生活の質を評価するMinnesotaスコア)の著明な改善、NYHA機能分類の有意な改善がみられた。CRTの運動耐容能に対する効果も同様で、ピーク酸素消費量(VO2)と運動時間の一致した改善がみられている。
さらに、CRTは疾患の自然歴にも影響するように思われる。Abraham博士のグループは最近Multicenter
InSync Randomized Clinical Evaluation(多施設共同InSync無作為臨床評価:MIRACLE)試験の成績を発表した。この試験では機能的エンドポイントが強調されたが、CRTによる心不全有病率の指標と死亡と入院を必要とする心不全の増悪を複合したエンドポイントの改善も明らかであった。
しかし、これらの結果はすべてを語るものではない。最近発表されたメタ解析ではMIRACLE試験のデータの所見にも触れられている。この解析では、心不全の増悪による死亡のリスクが51%減少したことが示されたが、CRTによって心不全に無関係な死亡率の改善はみられていない。博士は、この結果は心不全による死亡率は減少するが心臓突然死は改善しないことを意味するものである、と語った。
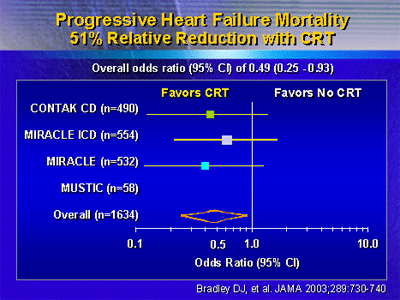
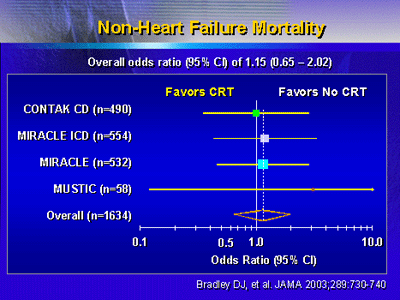
左室機能障害あるいは心不全を有する患者における植え込み式心臓除細動器(ICD)の使用に関しては多くの臨床試験がある。これらの試験では虚血性心疾患を有する患者が優先的に組み入れられている。非虚血性の心筋症患者が除外されることは結果に制約を加えることになるが、Abraham博士は、今や両群の患者で圧倒的なデータが集積されており、それぞれでCRTとICDの併用が有効であることが示されていると強く主張した。
画期的なMulticenter Automatic Defibrillator Implantation Trial-II(多施設共同自動式除細動器植え込み試験
II:MADIT II)試験が左室機能障害または心不全を有する患者に予防的にICDを使用する範例になったと思われる。左室駆出率が30%以下の虚血性心不全患者で総死亡が約31%減少したことが示されたのである。博士は、これらの試験結果は患者にとって非常に大きな福音となる、と語った。
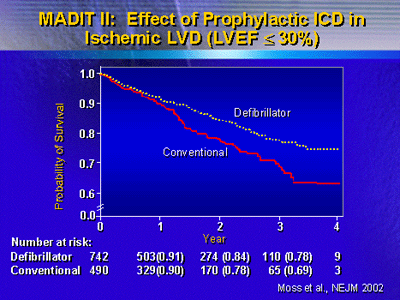
MADIT II試験のすべてのサブグループでICDは等しく有効であった。特に、サブグループ解析では、QRS幅が拡大している患者でその効果がより大きいことが示唆された。
しかし、ICDは主に心臓突然死による死亡率を低下させるが、ICDによって心不全の自然経過が修飾されたり、心不全の増悪による死亡率が低減されることはない、と博士は語った。実際に、MADIT
IIの成績によると、新しい心不全の発生やその増悪は通常の治療を受けた患者に比してICD群でやや多くみられている。
これらの所見に基づくと、CRTとICDの併用によって左室機能障害と心不全を有する患者の予後を最適に維持できることは明らかであると思われる。実際にACCで公表された新しいデータは、この見解に新たな支持を与えるものである。COMPANION試験では、1,600例以上の患者が、薬物治療のみ、CRT、またはCRTとICDの併用治療に割り付けられたが、CRTとICDの併用群で総死亡が43%というきわめて有意な減少を示した。それに対して、CRTによる治療だけを受けた患者では総死亡の減少は24%で有意ではなかった。
|