精神分裂病、双極性感情障害、自閉症などの深刻な精神疾患では、遺伝子組成が詳しく調べられている。これらの遺伝子組成はⅡ型糖尿病や心臓血管系疾患などの身体疾患より表出しやすいことが報告されている。遺伝的要因に強く影響を受ける精神疾患を徹底的に研究することで、病態生理学上の問題が明確になれば、薬を開発するのに役立つだろう。
アルツハイマー病は遺伝子の研究が新しい治療戦略の開発に貢献した一例である。アルツハイマー病がメンデルの法則に従って遺伝する、珍しい家系が見つかったことで、3つの遺伝子の変異が原因で病気が起こることが確認された。3つの遺伝子全ての変異から有害ペプチドが蓄積されることを発見し、有害ペプチドを構成するアミロイド前駆体の研究につながった。また、遺伝子的研究の進歩からヒトで生じる遺伝子の変異を持ったマウスを人為的に作ることが可能となった。このことにより免疫学的治療など、効果的な治療法の開発ができるようになった。
しかしアルツハイマー病は神経学的病理が明らかな(剖検によるものではあるが)独立した疾患単位であるが、精神分裂病や双極性感情障害、自閉症、不安障害、うつ病ではそのような限定的な特徴は存在しない。そこで、これらの疾患ではそのphenotype(表現型)を頼りに論じることしかできず、多くの難問が生じるのである。現在の精神医学の診断システムはDSMとICDの診断基準からなる。これらは行動学的特徴と予後の予測因子についてコンセンサスを提供しているが、この、専門家によるコンセンサスを物理的に実証
することはできない。したがって、精神科的診断は生物学的に意味のある表現型とは異なるのかも知れず、遺伝子研究に混乱を生じている可能性がある。
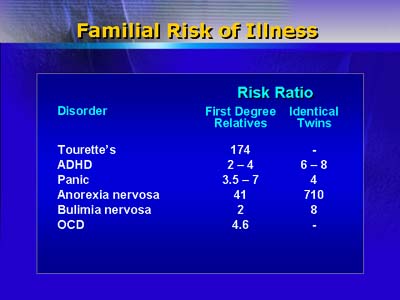
遺伝子型もまた、精神疾患の遺伝子研究を混乱させるものである。アルツハイマー病の研究の鍵は、メンデルの法則にのっとって遺伝する型の発見であった。一方、精神疾患への遺伝子の関与は複雑なようである。どの遺伝子も単一では病気を引き起こすための必要条件でも十分条件でもありえない。精神疾患は多くの遺伝子の相互作用と、非遺伝的要素がからみあって生じるものと考えられる。発病に至るには、複数の遺伝子的過程が関与している。さらに、精神疾患に関しては、Ⅱ型糖尿病における耐糖能の異常やアルツハイマー病におけるアミロイド斑のような明確な指標はまだみつかっていない。
ヒトゲノムプロジェクトにより、ヒトという種は非常に新しいものであり、個人と個人の間の遺伝子の変異は小さいということが明らかになった。対立遺伝子仮説が正しく、共通の病気は共通の遺伝子変異によって起こると証明できるのであれば、また、遺伝子変異の数に限りがあるのならば、その中から精神疾患を発症させるおそれのある遺伝子を探していくことになるのであろう。
現在、ポスト遺伝子時代においては、倫理的な問題は重要である。遺伝情報が保険会社や雇用者、政府などによって誤った使い方をされるおそれは十分にある。精神疾患では特に、遺伝情報は決定的なものというより可能性を示すのにとどまるだけに、情報の扱いは慎重にしなければならない。精神疾患はハンチントン病のように遺伝的に決定されるものではない。遺伝情報はプライベートなものにとどまるべきものである。