|
今日、心筋を虚血から護る最も重要な手立ては早期再灌流である。つまり閉塞血管をすばやく開き、灌流を維持することである。このために用いられる手段として大切なものは、血栓溶解療法、冠動脈形成術やステント留置術といった経皮的冠動脈インターベンション、アスピリン、ヘパリン、GP
IIb/IIIa受容体阻害薬である。
Kloner博士のグループは再灌流療法の治療効果がより向上するための補助療法の研究を進めてきた。今日まで、この分野に関する薬剤を用いた多くの研究がなされてきた。しかし、それらの多くは成功しなかった。白血球阻害薬、活性酸素スカベンジャー、補体阻害薬などである。医学雑誌によせられた報告は、これらの薬剤に関して否定的な結果であった。
Adjunctive Therapies that
have failed to
Reduce Infarct Size or Improve Outcome
| Inhibitors
of WBC adhesion |
HALT MI, LIMIT MI |
No reduction in IS |
| Calcium
blockers (Nifedipine) |
SPRINT-2 |
Increased mortality |
| h-SOD |
Flaherty JT, et al. Circulation 1994;89:1982 |
No increase in LV function |
| RheothRx
(poloxamer 188) |
CORE Study |
No difference in death, shock or re-infarction |
| Trimetazidine
(antioxidant) |
EMIP-FR |
No effect on mortality |
| Molsidomine
(nitric oxide donor) |
ESPRIM |
No effect on mortality or other clinical outcome |
| Fluosol |
TAMI-9 |
No reduction in infarct size or improvement
in LV function |
| Hyaluronidase |
Pre-thrombolytic era |
No effect on infarct size |
| Complement
Inhibition |
COMPLY Trial |
Complement activity blocked but no reduction
in infarct size |
|
しかし、いくつかの肯定的な結果を報じたものもみられる。急性心筋梗塞における早期のβ遮断薬静注療法に注目しているものもいる。多くの臨床試験から、急性心筋梗塞発症3〜5時間以内の早期のβ遮断薬投与が、梗塞サイズを縮小し、左室機能を改善し、再梗塞率の低下をもたらすとの予想が示された。さらにいくつかの研究では、早期のβ遮断薬静注は生存率をも改善する可能性を示唆した。
興味深い分野として、グルコース-インスリン-カリウム療法が挙げられる。最近の臨床試験では、急性心筋梗塞に罹患した糖尿病患者に対するグルコース-インスリン-カリウム療法は1年後の死亡率を改善した(18.6%
vs. 26.1% コントロール群、 p=0.03)。死亡率の差はその後も持続し、3.4年後も有意な改善効果を維持している。心血管系の危険因子が少なく、過去にインスリン療法を受けたことがない患者で、本療法の効果は最も顕著に現れた。また、他の報告によれば、急性心筋梗塞に対するグルコース-インスリン-カリウム療法は、急性心不全を合併しない患者においてのみ死亡率を有意に低下させた。
実験モデルでは、グルコース-インスリン-カリウム療法は梗塞サイズを縮小しないことから、Kloner博士は本療法の有用な効果には、抗不整脈作用の機序が介在する可能性を示唆した。
一方、いくつかの実験結果からアデノシンは梗塞サイズを縮小するといわれている。これは、アデノシンが虚血心筋のプレコンディショニングにおける経路で果たす役割と関連づけて理解される。さらに研究者の中には、アデノシンによる心筋再灌流傷害抑制効果を提唱するものもいる。この他にアデノシンには抗血小板剤としての性質もあり、同様に抗炎症作用を有する可能性も指摘されている。
二つの大規模試験AMISTAD IおよびIIでは、アデノシンを再灌流療法中あるいは再灌流前に投与した場合、前壁心筋梗塞の梗塞サイズを縮小した。AMISTAD
IIでは、アデノシンで悪質な心事故が減少する傾向もみられた。以上の観察結果に基づいて、Kloner博士は「もっとアデノシンに関する研究を積み重ね、検証することが必要である」と述べた。
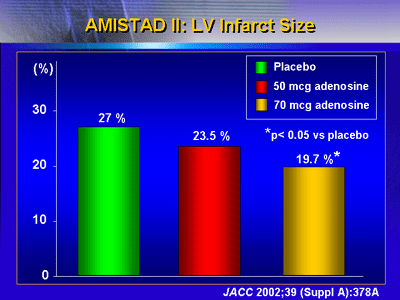
再灌流療法に低体温療法を付加した場合も、余剰の効果が期待できる。実験結果からは、虚血時の心筋冷却で、顕著な心臓保護効果が得られた。
Kloner博士のグループはウサギを用いた実験で、冠動脈閉塞時に虚血領域の温度を低下させた。この実験から、4℃の温度の低下で心筋の代謝速度は低下し、心筋細胞の壊死は減少することがわかった。
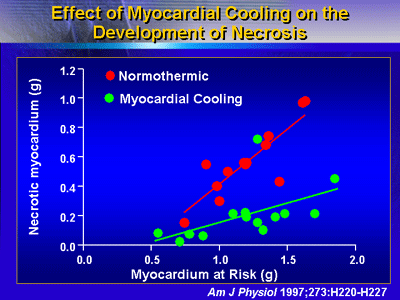
現在、低体温の臨床的有用性を検討する試験が計画中である。熱交換カテーテルを使用して低体温を誘導した最近の研究では、35℃以下の体温で梗塞サイズが縮小した可能性があることが示された。
CariporideのようなNa+/H+交換抑制薬は、実験モデルの梗塞サイズを著明に縮小した。実験は、冠動脈閉塞15分前にcariporideかプラセボをウサギに投与し、検討された。
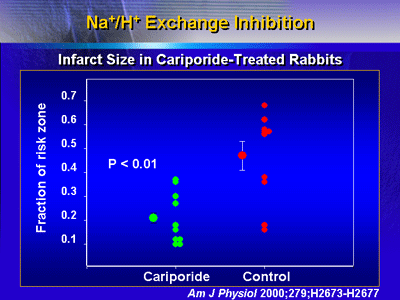
現在進行中のいくつかの臨床試験によって、この実験結果は強く支持されている。ある研究では、血管形成術の前にcariporideの投与を受けた患者は、梗塞サイズがより小さく、左室機能も改善していた。また、冠動脈バイパス術を受けた患者を対象にした別の研究でも、cariporideは有用な効果をもたらした。つまり、死亡率と再梗塞の低下をもたらしたのである。
研究者の中には他の心筋保護作用の可能性を有する薬剤、例えばマグネシウムのような薬、に着目しているものもいる。ATP感受性カリウムチャネル開口薬と呼ばれるグループに属する薬もたいへん有望視されている。急性心筋梗塞患者での使用例はいまだ報告されていないが、近い将来臨床試験が開始されるであろう。
今日の急性心筋梗塞治療は二つの大きな柱からなる。一つは、血栓溶解療法や血管形成術、ステント留置術の技術ですばやく冠動脈を開くことである。そしてもう一つはアスピリン、GP
IIb/IIIa受容体阻害薬や低分子ヘパリンで冠動脈の開存を維持することである。補助療法は、再灌流療法の効果をより一層飛躍させる治療法として登場することだろう。
|