| Acute Myocardial Infarction
STudy of ADenosine(AMISTAD)では梗塞サイズを評価するためにTc-99 sestamibiを用いた心筋灌流画像を使用している。この梗塞サイズがこの試験の一次エンドポイントであり、血栓溶解療法の補助薬剤としてのアデノシン(プリンヌクレオシド)を評価することになる。
Sestamibiの画像評価では通常2画像を計測評価する。急性期の灌流欠損画像では危機に瀕した心筋の領域を反映し、最低5日目以降の最終画像では心筋梗塞サイズを反映する。この2画像の差異は、それゆえに救出された心筋を表現することになる。
Sestamibi画像の評価の有効性はGibbons博士によれば数多くあるという。Sestamibiによる心筋梗塞サイズが小さいということと患者の予後が良く相関するなど、有効性を示すエビデンスは多数ある。
急性期のsestamibi画像は危機に瀕した領域を計算することができ、側副血行の評価が可能である。最終のsestamibi画像は、治療までの時間、梗塞サイズ、そして小梗塞、大梗塞といった差異のある評価にも良い。逆に、致死率に関しては単に治療までの時間的な評価ができるにすぎない。結果として、sestamibi画像試験は極めて数少ない評価で利益を証明しうるし、また直接かかるコストについても十分少なくてすむ。
Endpoints in MI Trials
| |
Sestamibi |
Mortality |
| Area at risk |
(Yes) |
No |
| Collateral flow |
(Yes) |
No |
| Time to therapy |
Yes |
Yes |
| Infarct size |
Yes |
No |
| Differential benefit |
Yes |
No |
| Patients required/arm |
140 |
10,000 |
| Cost ($ millions) |
2 |
≧ 35 |
|
Gibbons博士はMayo Clinicの彼の研究室が14の完成したsestamibi試験の中核研究室として貢献したと述べている。この中には、アデノシン/血管形成術を取り扱ったALIVE試験、そして再灌流様式としてのアデノシンと血栓溶解を評価したAMISTAD
IとIIがある。
アデノシン試験を無作為化する前に、Mayo Clinicは血管形成術とアデノシン療法に関して一施設のパイロット試験を実施している。この試験では、心筋救済効果が過去のコントロールに比較して極めて良いことを示した。
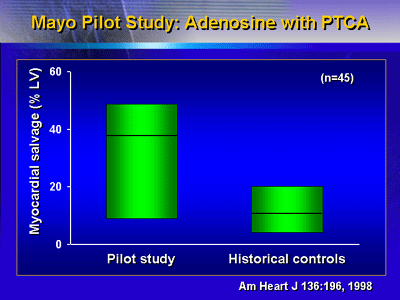
スポンサーは初期にこのパイロット試験を中止したものの、心筋の危機に瀕した部分がほとんど同一でありながら心筋梗塞サイズはアデノシン群で小さかった。しかし、サンプルの数が少ないとはいえ、この試験ではアデノシンが有用であるという統計的に強い傾向を示した。この結果を受けて、次に無作為化ALIVE試験が計画された。
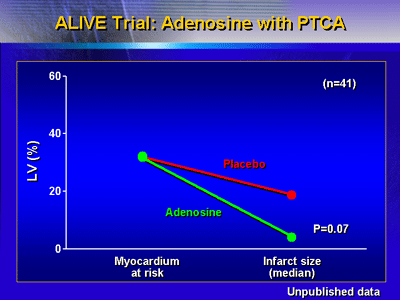
AMISTAD試験ではST上昇型の心筋梗塞236人を対象に、血栓溶解とアデノシンを評価している。経静脈的アデノシン注入(70mcg/kg/min)とプラセボ群で無作為化し、血栓溶解時に注入を開始して3時間これを持続させた。血栓溶解の薬剤はtPAが62%、ストレプトキナーゼが38%であった。一次エンドポイントはsestamibi画像評価による梗塞サイズである。
前壁心筋梗塞では、アデノシン注入群の梗塞サイズが小さかった(67%の減少、p<0.01)。逆に前壁心筋梗塞以外の梗塞では梗塞サイズに差異は認められなかった。下壁梗塞の過度な徐脈、あるいは血圧低下がこの悪影響を来した原因である可能性がある。
Gibbons博士は現状の治療では下壁梗塞サイズは小さすぎて、このような補助治療効果は出にくいと述べている。
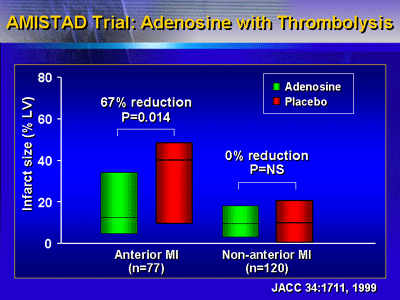
その次に出されたAMISTAD II試験では前壁心筋梗塞のみが対象となった。この理由はAMISTAD Iにおける下壁梗塞の効果が少ないことや悪影響を考えてのことである。
AMISTAD II試験では2,018人の患者を、70mcg/kg/minで注入する群、より低い注入量の群、そしてプラセボ群に無作為化し、再灌流後15分で開始、3時間持続投与した。試験担当者は患者を、死亡と新しい心不全発症というエンドポイントまで6ヵ月間観察した。243人のサブ解析ではsestamibiでの梗塞サイズを5日後に評価した。
残念ながら、6ヵ月の臨床的エンドポイントには差が出なかった。この結果は、低用量アデノシン、高用量アデノシンの両方をプールして解析したことに起因するであろう、とGibbons博士は述べている。ストレプトキナーゼを使用したことも一因と考えられる。
この検討では、82%のプラセボ群が6ヵ月間心不全症状なしで生き延びている。またプールされたアデノシン群では、心不全症状なしの生存率は84%であった。相対的リスク減少は11%でありこれは有意なものではなかった。アデノシンの用量別に評価したところ、高用量群に効果が強いことを見出している。しかし、この評価でもアデノシンの治療効果を証明するには至らなかった。
心筋梗塞サイズのデータはプラセボ群とプールされたアデノシン群では差がなかった。しかし、用量別に評価すると、高用量群で57%の相対的リスク減少が認められた。この結果は、AMISTAD
Iの梗塞サイズ減少効果が統計的に有意であったのと同一であった。
いくつかの試験デザイン項目にもかかわらず、このAMISTAD IIの結果はAMISTAD Iの梗塞サイズを十分減少させるという結果を補強していると考えられる。それゆえに、良くデザインされた臨床試験でアデノシンをさらに評価することは意味がある。しかし、商業ベースの興味が減少しており、そのような試験にはNHLBIなどの公的団体の援助が必要になるであろう。
|