|
Rajagopalan博士は開口一番、重症間欠性跛行における身体障害はIII度心不全患者のそれに匹敵することを示した。3分の2の患者は半街区に当たる距離を歩行することが困難である。
Regional Angiogenesis With Vascular Endothelial Growth Factor
in Peripheral Arterial Disease(末梢動脈疾患で血管内皮成長因子による局所の血管新生:RAVE)試験は血管内皮成長因子を筋肉内に注入することによって、障害肢に血管新生が誘発され、重症末梢血管障害を有する患者で、最長歩行時間、Gardnerのプロトコールによるトレッドミル運動負荷試験、あるいはその両者の改善がもたらされるかどうかを検討するものである。
血管内皮成長因子121はその遺伝子を複製機能が欠損したアデノウイルスに結合させて筋肉内に注入された。この技術は冠動脈や末梢血管の虚血を来した動物モデルで血管新生を誘発することが確かめられたものである。
対象患者は重症で、原則的に片側性で、障害肢への血流が維持されている末梢血管障害を有する患者であった。試験に組み入れられた患者では、ベースラインでトレッドミル運動負荷試験で1〜10分の最長歩行時間の測定が2回行われた両測定値の差は20%に止まった。治療の対象と考えられた患者ではアデノウイルスのタイター(Immunoglobulin
M)が1:50以下であることが必要とされた。
除外基準はがんや糖尿病性網膜症などの成長因子に関する一般的禁忌事項:cylostazolまたはpentoxyfyllineが投与されている患者はベースラインのスクリーニングの前1週間あるいはそれ以上の間治療を中止できる場合に限って組み入れた。
フローチャートに示すように、229例の患者が試験に登録され、105例が糖尿病の状態を考慮した上で、プラセボ、低容量遺伝子治療、および高用量遺伝子治療に割り付けられた。登録時の調査票をみると、ほとんどの患者が糖尿病(3群でそれぞれ、27%、25%、30%)、喫煙、高血圧、そして高コレステロール血症などの血管病に対する危険因子を複数もっていた。
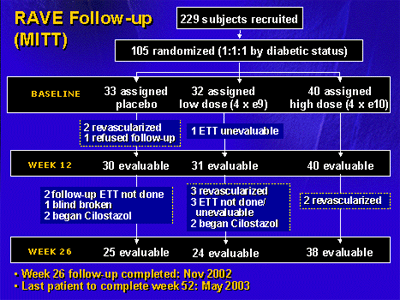
ベースラインにおける足首上腕係数を用いた循環試験では、3群すべてで実際に血管病変は主として片側性であることが示された。障害肢の足首上腕係数は平均で0.60、一方、他方の肢ではこの係数が有意に高かった(プラセボで0.80、低用量と高用量の遺伝子治療群で0.90であった)。
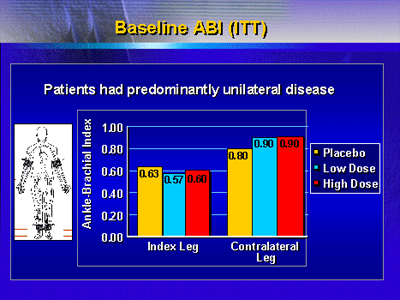
治療開始後30日目の安全性に関するデータは、注入部位の細胞炎を来した症例はなく、血液検査で肝機能試験値の上昇や骨格筋酵素の増加もみられずきわめて良好であった。障害肢に用量依存性に浮腫がみられた。プラセボ群と低用量群の浮腫は軽度であったが、高用量群で中等度から重度の浮腫を来した症例があった。両側に浮腫を来した症例はなかった。

12週における臨床的エンドポイントの評価成績は失望させるものであった。3群すべてで最長歩行時間と間欠性跛行の発症時間には同程度の増加がみられた。安静時と運動後の足首上腕係数は3群いずれにおいても時間の経過による変化はみられなかった。機能レベルの臨床的評価に関しては、3群すべてでベースラインに比して明らかな改善がみられた。26週目における評価でもパターンは同じであった。
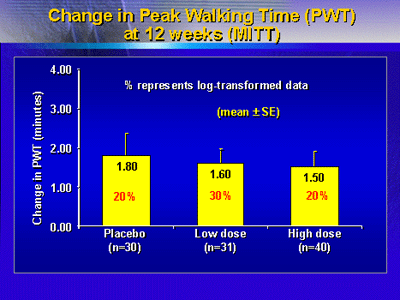
RAVE試験は、今日までに心血管系疾患を有する患者を対象にして行われたアデノウイルスによる遺伝子治療のプラセボ対照試験の中で最大規模のものである。浮腫が高用量群でより頻回にみられ、やや重症であったが、遺伝子治療は52週の追跡期間を通して安全であることが示された。最も期待はずれであった所見は大きな陽性プラセボ効果であった。ベースラインから26週に至るまで、いかなる主要および副次的エンドポイントに関しても治療効果がプラセボに優るという証拠は認められなかった。
|