|
心筋梗塞後の心不全で最も大きな問題は、心筋が消失し線維性瘢痕組織に置換されることである。最近の生命工学の進歩によって失われた左室収縮要素を回復させる試みが可能となった。この方法による心筋梗塞後心不全患者の収縮機能の回復が期待されている。
収縮機能障害を改善するために用いることができるものとしていくつかの細胞が考えられている。例えば、幹細胞、心筋細胞、あるいは線維芽細胞などである。Siminiak博士らは失われた心筋を自己の筋原線維によって置換する可能性を検討している。
この試みに自己由来の細胞を用いることにはいくつかの利点がある。免疫抑制療法を行う必要がない。細胞の供給に問題がない。さらに自己由来の細胞を使用する場合には胚細胞や胎児性細胞の使用につきまとう倫理的な問題がない、などの利点である。
動物実験のデータからは、心筋梗塞の瘢痕組織の中に移植された骨格筋筋原細胞は心筋細胞様のエレメントを形成し機能が回復する可能性が示された。種の異なる多くの動物でも同じ所見が再現された。Hagège博士らはヒツジで自己骨格筋筋原線維移植の効果を報告している。
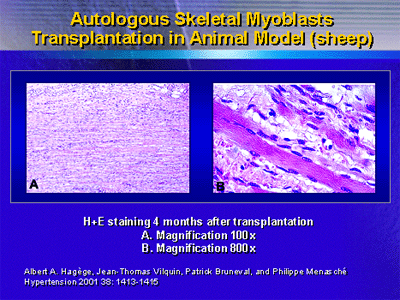
Siminiak博士らのグループは冠動脈バイパス手術を行う際に自己骨格筋筋原細胞移植の安全性と実現可能性とを検討する第I相の臨床試験を独自に開始した。この試験には手術が予定されている10例の患者が組み入れられた。すべての患者で左室の1から3セグメントで収縮の消失(akinesia)か収縮異常(dyskinesia)がみられた。
各々の患者で外側広筋から約1cm3の筋標本が採取された。筋原細胞を単離して3週間細胞培養が行われた。得られた筋原細胞はバイパス手術を行う間にakinesiaあるいは
dyskinesiaを呈する部位の心筋内に注入された。
1例は処置を行った後7日目に死亡した。剖検では以前に正常収縮を示していた部位に新しい心筋梗塞が認められた。この新しい梗塞は細胞移植とは関係はないと考えられ、試験は継続された。
残りの9例で駆出率の増加がみられたことは以前に報告されている。今回のACCでは、博士はこの改善がその後12ヵ月の経過観察においても持続してみられたことを報告した。
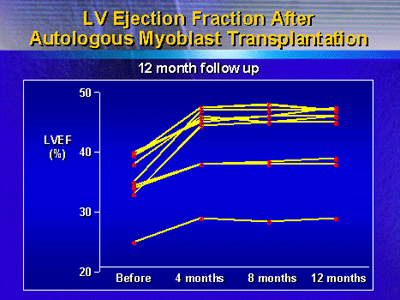
さらに、5ヵ月目に局所セグメントの収縮機能の変化も解析された。博士によると、9つのdyskinesiaを示した部位の内5つがakinesiaとなり、akinesiaであった10のセグメントの内4つがhypokinesia(収縮減少)に改善したという。
最初の2例では重度の心室頻拍がみられたので、予防的にアミオダロンが使われることになった。その後の患者ではこのような持続的心室頻拍はみられていない。わずか2例ではあるが、アミオダロンが経口的に2ヵ月間続けられた。3ヵ月間アミオダロンの投与が続けられた患者はいない。
これらの結果から自己骨格筋筋原細胞移植は少なくとも実現可能であることが示唆される。しかし、問題も多く残っている。この治療法はさらに検討を続けてその有効性を確証し、臨床応用がどこまで可能かを確立しなければならない。例えば、第II相試験によって、移植後の左室挙動の改善に関するデータを提供することも必要であろう。
|